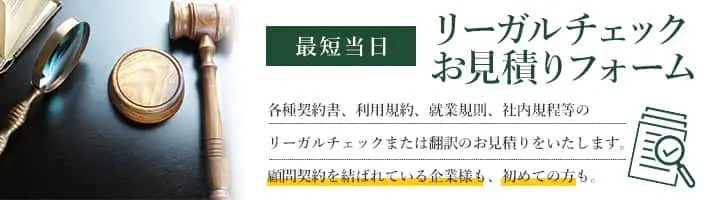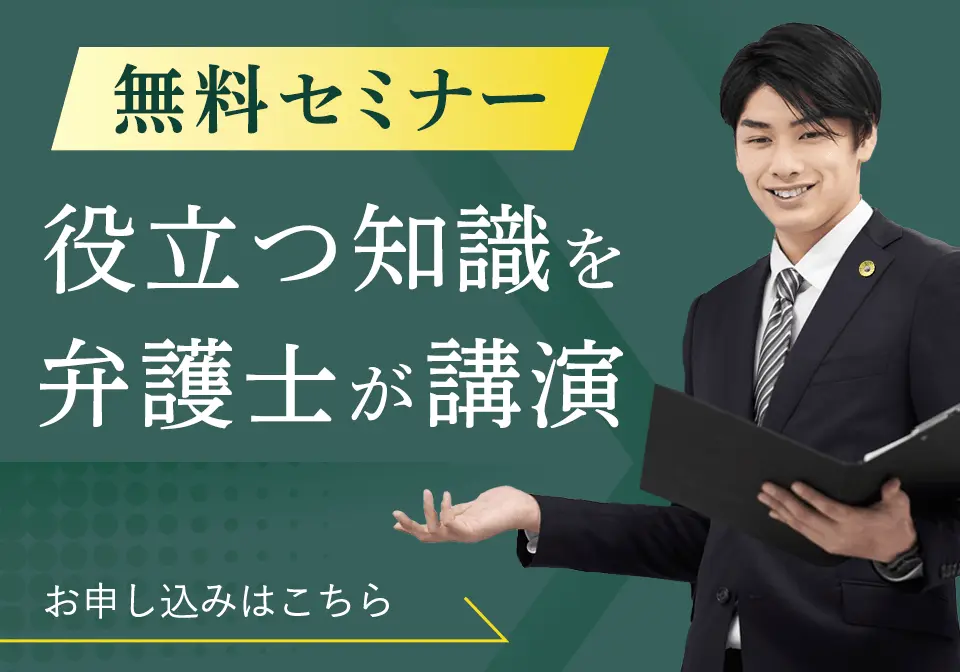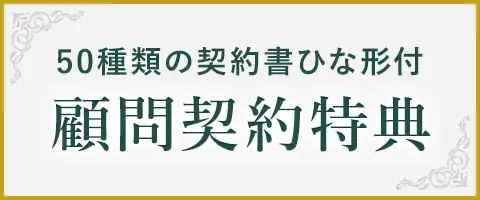- 企業法務・顧問弁護専門サイト
- 企業法務コラム
- 労働問題
- 問題社員を辞めさせる方法が知りたい! 違法にならずに退職させる方法は?
問題社員を辞めさせる方法が知りたい! 違法にならずに退職させる方法は?

会社に問題社員がいて、給料分の働きをしないどころか、次々と問題を引き起こしているような場合には、一刻も早く辞めさせたいと考えることでしょう。
しかし法律上、使用者が労働者を解雇により辞めさせるハードルは非常に高くなっています。そのため、問題社員を辞めさせる際には、法律を踏まえた慎重な対応が求められます。
この記事では、会社の問題社員を辞めさせる方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、会社を悩ます問題社員の特徴4つ
会社の問題社員の行動パターンはさまざまですが、その中でも代表的な4つをピックアップして紹介します。
-
(1)職務怠慢
職務怠慢で給料分の働きをしない社員は、会社にとっては頭が痛い存在です。
特に、- 無断欠勤をする
- 正当な理由のない遅刻や早退をする
- 離席が不相当に多い
などのケースでは、従業員としての義務を果たしていないと評価されても仕方ありません。
これらのケースは、いずれも就業規則違反に該当し得るため、使用者側から従業員に対してなんらかの懲戒処分を行うことができる場合があります。 -
(2)著しい能力不足
他の従業員に比べて著しく能力が低く、基本的な業務さえ満足にこなせない社員は、ほかの従業員の足を引っ張る分、会社にとってマイナスな存在であるとさえいえるでしょう。
単に仕事に慣れていないというだけなら改善の余地はありますが、再三指導を行ったり、研修を受けさせたりしたにもかかわらず全く改善の兆しを見せないという場合は、どうにかして辞めさせる方法を検討したいでしょう。 -
(3)過剰に権利を主張する
会社の従業員には、労働契約や労働基準法その他の法令によって、さまざまな権利が認められています。
しかし、ささいな会社の不手際を声高に言いはやしたり、上司からの指示をなんでもすぐにパワハラ呼ばわりしたりする社員は、会社に協力する気がない問題社員と評価すべきでしょう。
こうした社員は、権利を盾にしている分、経営者や上司にとっても非常に扱い方が難しい存在です。 -
(4)社内の秩序を乱す
周りの同僚にセクハラやパワハラを行って社内の秩序を乱す従業員は、使用者にとってもっとも悪質な部類の問題社員といえるでしょう。
こうした問題社員を放置していると、他の従業員が精神を病んで辞めてしまうリスクもあるため、早急に辞めさせるなどの対応が必要です。
問題社員のトラブルから、
2、問題社員への適切な対応方法
問題社員にはすぐに辞めてもらいたいと考えるのもわかりますが、労働法規による解雇規制が非常に強力なことを考えると、解雇は最終手段であると考えなければなりません。
解雇をする前に、使用者側が問題社員に対してとるべき対応について解説します。
-
(1)上司から注意・指導を行う
基本的なことではありますが、やはり問題社員に対しては、根気強い注意や指導を行うことが第一の対処法になります。
まずは上司から注意・指導を行いますが、上司だけで荷が重ければ、他の部署の管理職や、問題社員と年の近い先輩などにも協力を仰いで更生を促しましょう。
もし将来的に問題社員を解雇したいと考えていた場合にも、「注意・指導を行ったけれど全く改善の見込みがなかった」という事実を積み重ねていくことで、解雇が適法であると認められやすくなる可能性もあります。
能力不足の問題を抱えている社員に対しては、業務に必要な能力を具体的に言語化・数値化をしてから、どの能力がどのくらい欠けているのか、伝えるのがおすすめです。
基準があることで、能力不足の社員と会社とで認識を一致させることができますし、その社員の意識改善の助けにもなるでしょう。
指導をした結果、どのような改善が見られたか(または見られなかったか)といった記録もつけておきましょう。この記録は指導を振り返るときや改善が見られなかった場合の処分の根拠として役立つだけでなく、その後トラブルがあった場合の証拠にもなります。
また、能力不足の社員が、
・育成が必要な新卒社員であった場合
・中途で採用された社員であった場合
とでは、その対応を大きく変えなければなりません。・新卒社員の場合
新卒社員の場合、その多くは社内で社員を育成することが前提で採用されています。
そのため、新卒社員を能力不足だとして解雇した場合、本当に必要な教育を行ったのか、審判や裁判の場では厳しく判断されることになるでしょう。そのことも頭に入れつつ、指導をする必要があります。
・中途社員の場合
一方で、業務に必要な技能や社内での役割を明確にしたうえで、採用された中途社員の場合には、改めて必要な技能や役割を確認しつつ、指導を行いましょう。こちらの場合は、新卒社員よりも、能力不足の判断基準が明確であるため、十分な指導をしたが解雇に至った場合に、新卒の場合よりは、その解雇が妥当であったと認められる可能性が高くなります。 -
(2)人事面談を行う
問題社員と人事部の面談をセットし、現状の人事評価について正式に問題社員に伝える方法も考えられます。
周囲からの評価がよくないことを直接聞かされれば、ある程度改善に向けた動きが見られるかもしれません。
これ以上勤務態度の悪い状態が続くようであれば、懲戒処分を検討せざるを得ない旨を伝えておくと、問題社員の危機感をあおることにもつながります。
また、その社員の特性が生かせる部署への異動可否も検討し、本人の希望も面談の場で確認しましょう。 -
(3)懲戒処分を行う
注意・指導・面談・異動などによっても改善の兆しが見えない場合には、懲戒処分により具体的な制裁を科すことも検討すべきです。
ただし、懲戒処分を行えるのは、就業規則などに規定される懲戒事由に該当する場合に限られます(就業規則のある会社では、就業規則に懲戒の事由及び程度を定めておくことが必要となります(労働基準法第89条9号))。
さらに懲戒処分については、労働契約法において次のルールが規定されています。労働契約法第15条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。懲戒処分を行う際には、上記の懲戒処分の要件を満たしているかどうか、法的な観点から慎重に検討することが必要です。
3、まずは自主退職を促す「退職勧奨」を
問題社員を辞めさせる際には、いきなり解雇するのではなく、自主退職を促す「退職勧奨」を行う方が安全です。
-
(1)退職勧奨とは?
退職勧奨とは、文字通り「退職を勧める」という意味で、会社が従業員に自主退職を促し、従業員がそれに応じて退職するという形態です。
退職勧奨は、会社側が一方的に従業員を辞めさせる「解雇」とは異なり、従業員が同意のうえで自主的に退職します。
そのため、後から労使間の紛争が再燃する可能性が解雇する場合と比べて低いので、会社にとってはいわば後腐れなく従業員を辞めさせることができるメリットがあります。 -
(2)退職勧奨の手順・方法
退職勧奨の手順や方法については、特に決まったルールはなく、会社側が何らかの方法で従業員に「辞めてほしい」旨を伝えることになります。
その際、従業員にとっても退職するメリットがあるように、上乗せ退職金などの提案が行われる場合が多いようです。 -
(3)退職勧奨を行う際の注意点
退職勧奨を行う場合の最大の注意点は、退職勧奨に応じるかどうかは従業員の任意であり、無理やり辞めさせてはならないということです。
たとえば、
・退職勧奨に応じなければ解雇だと脅す
・大人数で威圧的な説得を行う
・パワハラ的な言動で精神的に追い詰める
・閑職に追いやって仕事を与えない
などの方法を用いて従業員を辞めさせる場合、事実上強制的に辞めさせたと判断される可能性があります。
強制的に従業員を辞めさせるということは、会社が従業員を一方的に辞めさせる解雇と実質的に同じですので、解雇に関する法規制が適用されてしまいます。
そうなると、不当解雇と判断されてしまうリスクが非常に高まってしまうでしょう。
それだけでなく、パワハラ的な言動などを用いた場合には、そのことに対する損害賠償請求(慰謝料)をされるリスクも生じます。
このような事態が生じないように、退職勧奨は従業員の任意性が最大限に確保できる方法により行うことが大切です。 -
(4)社員が退職勧奨に応じない場合はどうする?
従業員が退職勧奨に応じない場合は、別の方法を模索するほかありません。
すぐに解雇して辞めさせる方法が念頭に浮かぶと思いますが、解雇の要件を満たしているかどうかを慎重に検討する必要があります。
あくまでも解雇は最終手段であって、配置転換をしたり、上乗せ退職金を増額して引き続き退職勧奨を行ったりするなど、よりマイルドな方法を模索する方が無難です。
どのような方法が適切なのかについては、弁護士に確認することをおすすめいたします。
4、問題社員の解雇は慎重に! 注意点を解説
労働契約法第16条により、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効」とされています。
そのため、たとえ問題社員であっても、解雇をする際には極めて慎重な検討が必要になります。
-
(1)解雇が有効と判断されるためのポイントは?
問題社員の解雇が有効となるためには、就業規則に定められる解雇事由(普通解雇の場合)または懲戒事由(懲戒解雇の場合)に該当することが必須です。
このうち懲戒解雇の場合は、さらに懲戒解雇相当の重大な違反行為があったかどうかが判断されることになります。
また、普通解雇・懲戒解雇のいずれについても、労働契約法第16条の規定に従い、解雇に客観的に合理的な理由があり、かつ解雇が社会通念上相当と認められることが要求されます。 -
(2)解雇が有効と判断される可能性が高いケース
具体的には、
・度重なる注意、指導にもかかわらず、業務態度改善の見込みがない
・周囲の従業員に対する悪影響が著しいと客観的に認められる
・就業規則に対する複数の違反が恒常的に見られる
などの事情があれば、解雇が合理的かつ社会通念上相当と認められる可能性が高いでしょう。 -
(3)解雇予告手当の支払いに注意
なお、どのような理由による解雇でも、よほど例外的な事情がない限り、30日以上前の予告または30日分以上の平均賃金に相当する解雇予告手当の支払いが必要です(労働基準法第20条第1項)。
5、不当解雇と判断された場合の会社側のリスクは?
上記の解雇要件を満たさないにもかかわらず問題社員を解雇し、問題社員による不当解雇の主張が認められてしまうと、会社は以下のリスクを負うことになります。
-
(1)問題社員を会社の従業員として復帰させなければならない
不当解雇は法的に無効なため、問題社員を会社の従業員として復帰させる必要があります。
-
(2)未払い分の賃金全額を支払う義務を負う
不当解雇後、問題社員に対して支払っていなかった賃金の全額を支払わなければなりません。
-
(3)不当解雇を行った企業として社会的評判が毀損される
もし不当解雇をした事実がインターネットなどで拡散されてしまうと、会社の評判に傷がついてしまう可能性があります。
6、解雇する際は事前に弁護士に相談を
再三解説したように、法律上、会社が従業員を解雇するハードルは非常に高いのが現実です。
そのため、問題社員を辞めさせることを検討している場合でも、すぐに解雇してしまうのではなく、どのような方法をとったらよいか事前に弁護士に相談することをおすすめいたします。
弁護士からは、問題社員のこれまでの行動や、会社の就業規則の内容などを考慮して、穏便に問題社員を辞めさせる方法についてアドバイスを受けることができます。
後に問題社員との間で紛争を発生させないためにも、一度弁護士にご相談ください。
問題社員のトラブルから、
7、まとめ
問題社員に対する注意・指導や退職勧奨が奏功しない場合には、解雇も選択肢に入ってきます。しかし、解雇は法律上の要件がとても厳しいので、安易な解雇は禁物です。
問題社員への対応に悩んでいる会社担当者の方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所では、問題社員を穏便に辞めさせる方法などについて、労働問題専門チームが専門的な知見を踏まえてアドバイスいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

- 内容・ご事情によりご相談をお受けできない可能性もございます。
- ご相談者様が、法人格のない個人事業主様の場合、初回相談は有料となります。
同じカテゴリのコラム
-

減給は10分の1までしかできない? 減給の上限をケース別に解説
2025年06月30日- 労働問題
企業では従業員の不祥事や職務懈怠、能力不足、あるいは会社の業績不振など、様々な理由で従業員の減給を検討することがありますが、無制限に減給できるものではありません。減給の方法によっては、法律で「10分…
- 減給
- 10分の1
-

転勤を拒否する従業員を解雇できる? 解雇以外の正しい対処法も解説
2025年06月26日- 労働問題
会社が転勤を命じたにもかかわらず、従業員が転勤を拒否するケースも珍しくはありません。従業員にも諸事情はあるでしょうが、会社としては業務上の必要性から転勤を命じているのですから、従業員の個人的な都合を…
- 転勤
- 拒否
- 従業員
- 解雇
-

労務管理とは? ずさんだとヤバい? 人事・労務管理者の基礎知識
2025年06月23日- 労働問題
「労務管理」とは、従業員のさまざまな事項全般を管理する業務です。適切な労務管理ができていない企業では、労働者が気持ちよく働くことができません。そのため、生産性の低下や離職者の増加などにつながるリスク…
- 労務管理とは
企業法務コラム
- 企業法務・顧問弁護専門サイト
- 企業法務コラム
- 労働問題
- 問題社員を辞めさせる方法が知りたい! 違法にならずに退職させる方法は?
お問い合わせ・資料請求