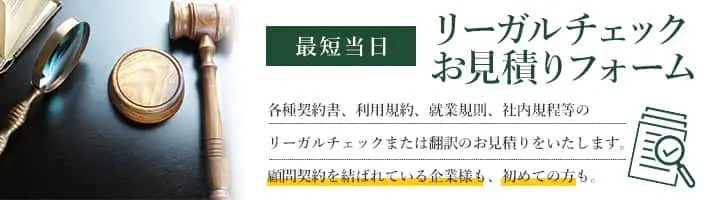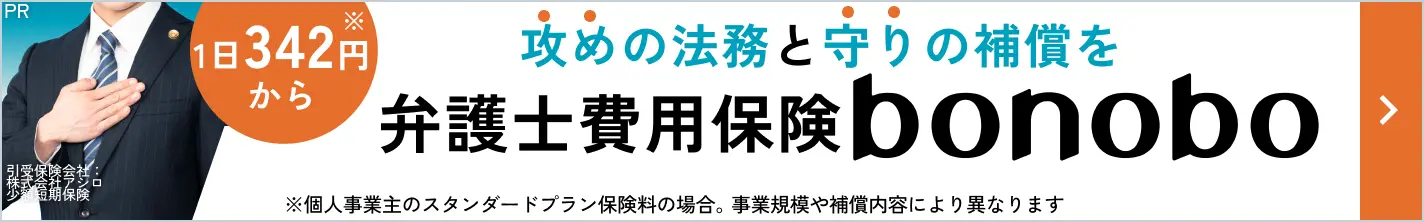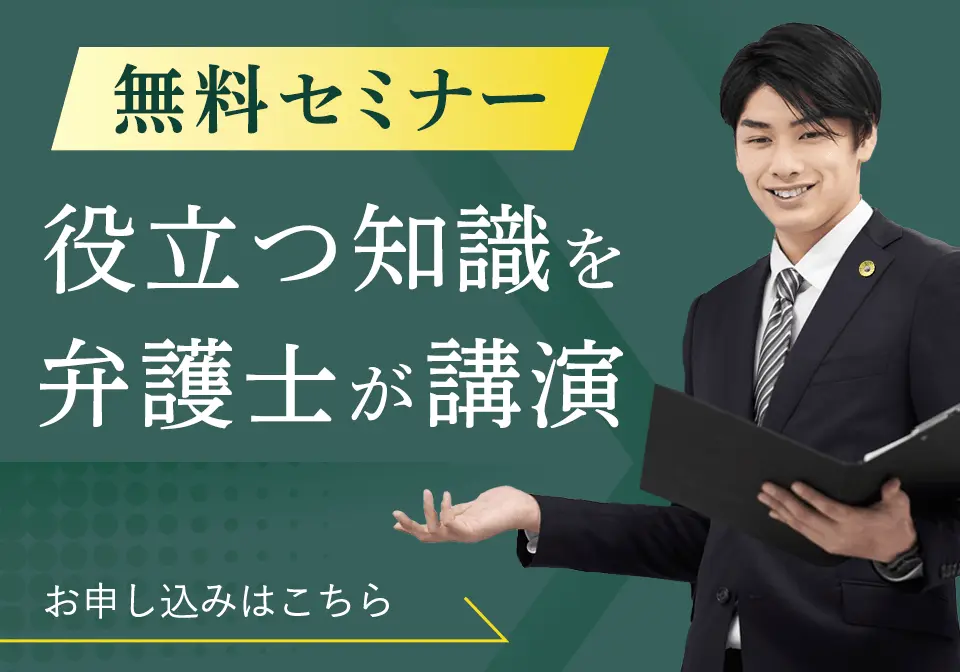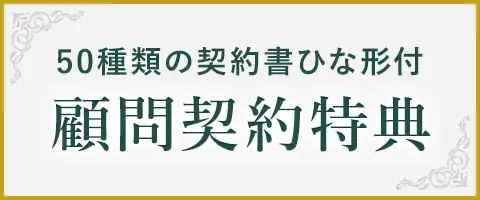- 企業法務・顧問弁護専門サイト
- 企業法務コラム
- 商標・特許・知的財産
- 特許法改正|査証制度の概要。 その要件と手続の流れについて
特許法改正|査証制度の概要。 その要件と手続の流れについて

査証制度とは、特許権などの侵害訴訟において、中立な立場の査証人が特許権の侵害立証に必要な調査を行い、その証拠を収集するための手続きとして新たに制定されたものです。
査証制度によって、特許権者にはどのようなことがもたらされるのでしょうか。本記事では、特許法改正における査証制度の新設について、その概要や具体的運用について説明します。
1、査証制度導入の背景
令和元年5月17日に特許法の一部を改正する法律が公布され、令和2年4月1日から一部を除き施行されていたところ、同年10月1日には査証制度が施行されるに至りました。
民事訴訟の原則に鑑みれば、特許権侵害訴訟においては、原告である特許権者が被告である被疑侵害者による特許権侵害及び損害を主張・立証しなければなりませんが、その証拠は多くの場合被疑侵害者側にありますので、立証は容易ではありません。
こうした偏りを是正するため、特許法(以下単に「法」といいます)は、従来から、損害額の推定規定(法第102条)や侵害者の過失の推定規定(法第103条)、書類提出命令や検証物提示命令(法第105条)を定めていました。
ただ、法第105条の制度は、書類や物品自体を調べるという点では一定程度有効であるものの、物の製造方法の特許やソースコードが争点となるソフトウェア特許等については十分に機能しているとはいい難い面がありました。
このような課題を踏まえ、今回の改正により、専門家(査証人)による法的拘束力を有する証拠収集手続として、査証制度が創設されることとなりました(法第105条の2以下)。
この制度は、特許権者の申し立てにより、裁判所が専門家(査証人)を指定し、指定された査証人が被疑侵害者の工場等へ立ち入り調査したうえで、報告書を提出するという証拠収集手続になります。
どのような人物が査証人として指定されるのかについて、法は「査証人は、裁判所が指定する。」とだけ定めており(法第105条の2の2第2項)、具体的な資格や資質については一切言及していません。しかし運用上は、特許権侵害訴訟の分野に応じて、当該分野の専門的知見を有する弁護士、弁理士、学識経験者等を査証人とすることが想定されています。
2、査証制度の要件
法第105条の2第1項は、以下のとおり定めています(下線部の括弧書きは筆者挿入)。
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において(必要性)、特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ(侵害の蓋然性)、かつ、申立人が自ら又は他の手段によっては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは(補充性)、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない(相当性)。
この条文から、裁判所は、特許権者(申立人)からの申立てを受け、被疑侵害者(相手方)の意見も聴取した上で、
② 侵害の蓋然性
③ 補充性及び ④ 相当性の四要件が満たされる
と判断した場合、査証命令を発令することがわかります。
査証制度は、裁判所の命令により、査証人が相手方の工場等に立ち入って特許権侵害の有無に係る証拠を収集する手続ですから、相手方にとっては大きな負担となります。そのため、これら四要件を充足することが必要とされています。
① 必要性は、査証制度の濫用を防ぐ意味でも当然求められる要件です。
② 侵害の蓋然性ですが、より具体的には、相手方から任意に提出された又は書類提出命令の結果得られた書類等の証拠によって、相当程度権利侵害の可能性が認められるが、その立証のためには査証によって更に証拠を得る必要がある場合に認められます。
③ 補充性ですが、補充性の要件を余りに厳格に解すると、せっかくの新制度が有名無実化してしまいますので、必ずしも書類提出命令等の手続を経た後でなければ補充性の要件を満たさないというものではなく、他の手段では十分な証拠を収集することができないと見込まれ、かつ、査証によって、より直截的かつ効率的に証拠を収集できる場合には、補充性の要件を満たすものと解されます。
④ 相当性については、相手方が不相当であることを主張・立証すべき(申立棄却事由)として運用されることが想定されています。
3、査証手続の流れ
① 申立人は、2.で述べた四要件を踏まえて、書面により査証の申立てをします(法第105条の2第2項)。これを受け、裁判所は相手方の意見を聴取し、当該四要件の充足性の有無を判断したうえで、査証命令の申立てを認容する決定、棄却する決定又は却下する決定をします。
これらの各決定に対して、申立人及び相手方は、即時抗告により不服を申し立てることができます(法第105条の2第4項)。
② 査証命令の申立てが認容で確定すると、査証人(と執行官)により、査証が実施されます。法には申立人や申立人代理人が査証に立会うことを認める規定はありません。
相手方には、査証協力義務がありますので、「正当な理由なくこれらに応じないとき」即ち不当に立入り要求を拒んだり、提出すべき書類を滅失させたりしたような場合には、裁判所は、立証されるべき事実に関する申立人の主張を真実と認めることができます(法第105条の2の5)。
③ 査証実施後、査証人は、裁判所に対して、査証報告書を作成・提出します(第105条の2の4)。そして、裁判所は、「査証を受けた当事者」(相手方)に査証報告書の写しを送達します(法第105条の2の6第1項)。
相手方は、送達から2週間以内に、査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しないことを申し立てることができます(同第2項)。というのは、査証報告書には、侵害立証には関係のない相手方の営業秘密等が含まれてしまう場合があり、それを申立人に開示することまでは許容し難いからです。
非開示の申立てがあり、「正当な理由」があると認められる場合、裁判所は査証報告書の全部又は一部を非開示にすることができます(同第3項)。なお、「正当な理由」の判断は、侵害立証のための必要性と秘密保護の必要性を比較衡量するものとされています。
非開示の決定又は非開示の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告により不服を申し立てることができます(同第5項)。
全部又は一部を非開示とする決定が確定した場合、当該部分が黒塗りにされた上で査証報告書が開示され、開示された報告書が証拠として採用されることになります。
なお、申立人と相手方は、査証報告書の閲覧等を請求することができますが、営業秘密等が含まれている場合があることから、それ以外の者が閲覧等の請求をすることはできません(法第105条の2の7第1項、第2項)。
査証制度が裁判実務においていかに活用されるのか、今後の運用が注目されます。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- 内容・ご事情によりご相談をお受けできない可能性もございます。
- ご相談者様が、法人格のない個人事業主様の場合、初回相談は有料となります。
同じカテゴリのコラム
-

著作権の種類│企業が知っておくべき著作権の基礎知識
2025年06月26日- 商標・特許・知的財産
多くのビジネス分野において、事業活動と著作権などの知的財産は切っても切り離せない関係にあります。そのため、自社の情報・コンテンツを適切に保護し、他社の著作権を侵害しないためにも、企業内で著作権の種類…
- 著作権
- 種類
-

AI生成物に著作権はある? 勝手に学習すると著作権侵害? 注意点を解説
2025年06月16日- 商標・特許・知的財産
文章・画像・動画などのコンテンツを作成する際に、生成AIが活用される頻度が増えています。生成AIを活用する際には、著作権の取り扱いについて気を付けなければなりません。学習・開発の段階と生成・利用の段…
- AI
- 著作権
-

商標権侵害を受けたらどうする? 所属タレントに関する権利の注意点
2023年12月25日- 商標・特許・知的財産
所属タレントの名前や写真の無断使用は、商標権侵害やパブリシティ権侵害に当たる可能性があります。これらの権利侵害を受けた場合には、速やかに差止請求や損害賠償請求などの対応を行いましょう。本記事では、タ…
- 商標権侵害
企業法務コラム
- 企業法務・顧問弁護専門サイト
- 企業法務コラム
- 商標・特許・知的財産
- 特許法改正|査証制度の概要。 その要件と手続の流れについて