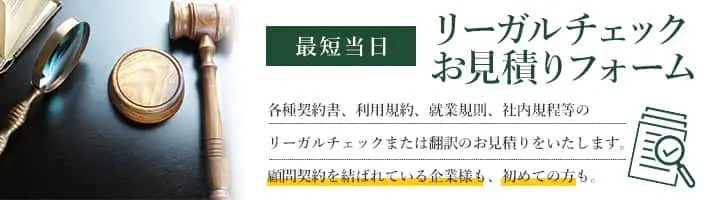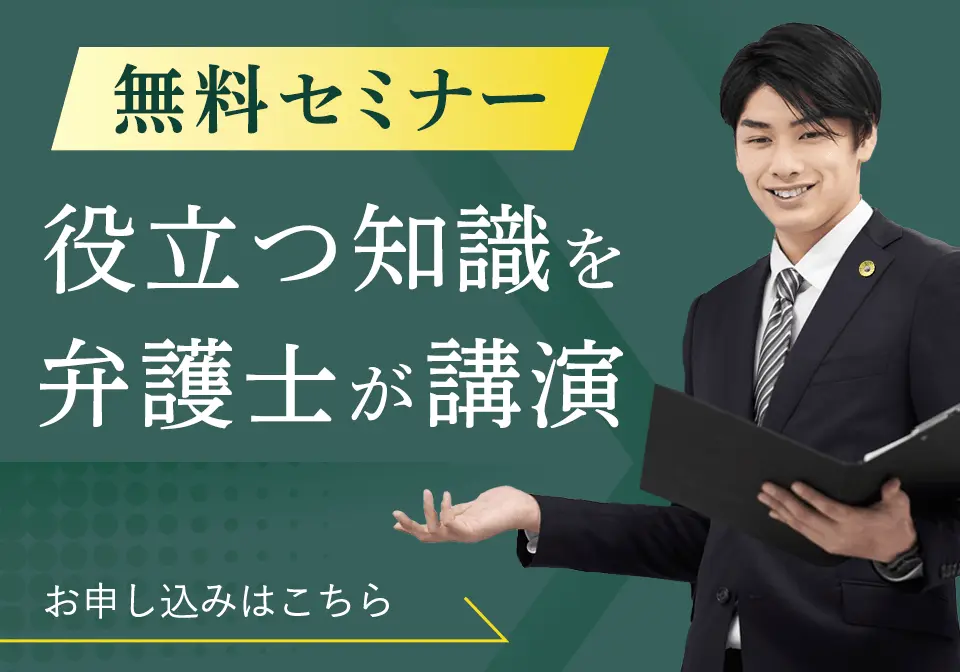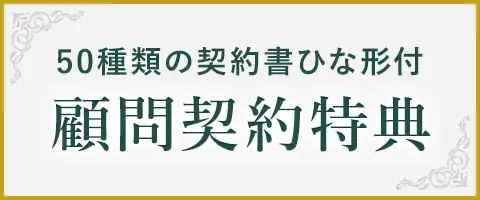- 企業法務・顧問弁護専門サイト
- 企業法務コラム
- 労働問題
- 育児時間とは? 従業員から申請される前に会社が確認しておくべき基本的事項
育児時間とは? 従業員から申請される前に会社が確認しておくべき基本的事項

いわゆる保育園待機児童問題を背景に、満1歳の誕生日を待たずして、保育園に入園できるタイミングで職場復帰する女性が増加しているといわれています。
こうした社会情勢を背景として、改めて、1歳未満の子どもを抱える女性労働者の育児と仕事の両立支援策として「育児時間」が注目されています。ところが、これまで「育児時間」制度の対象者は育児休業中であることが多かったため、「育児時間」の取得実績のない会社も少なくないと思われます。
そこで、本稿では、「育児時間」について概説した上で、事業主や企業の人事担当者の方がとるべき対応策について検討したいと思います。
1、育児時間とは
「育児時間」とは、労働基準法67条において、次のとおり定められています。
第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
すなわち、「育児時間」とは、1歳未満の子どもを育てる女性が請求した場合、使用者は、通常の休憩時間(1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上。労働基準法34条1項)の外に、1日2回、それぞれ少なくとも30分以上の子育てするための時間を与えなければならないとする制度です(労働基準法67条)。
なお、「1日2回各々少なくとも30分」は、8時間労働を想定して設定されているものなので、労働時間が1日4時間を下回るような場合には、「育児時間」の付与は、1日に1回で足りるとされています(昭和36年1月9日基収第8996号)。
そして、使用者が労働基準法67条の義務に違反した場合には、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されることがあるので、注意を要します(労働基準法119条1号)。
問題社員のトラブルから、
2、よくある質問(FAQ)
「育児時間」に関して、制度にあまり馴染みのない労務担当者の方などから、比較的よくご質問いただく事項について概説します。
-
(1)「育児時間」の請求権者
「育児時間」の請求権者法律上、「育児時間」の請求権者は、1歳未満の子どもを育てる女性に限られます。したがって、仮に1歳未満の子どもを養育していても、男性労働者には、労働基準法67条1項に基づく請求権は認められないことになります。
性別により請求権の有無が区別されている理由は、「育児時間」の立法趣旨がもともと授乳の時間確保にあったことに由来します。
他方、個社の事情に合わせて、就業規則上、1歳未満の子どもを育てる男女に「育児時間」を付与することは妨げられません。
なお、「育児時間」の請求権は、雇用形態(いわゆる正社員、契約社員、アルバイト・パートタイム労働者など)によって制限されていません。 -
(2)「育児時間」中の給与
「育児時間」中の給与「育児時間」中の給与については法律上定めがなく、専ら労使間の個別協議に委ねられています(昭和25年7月22日基収第2314号)。
そのため、「育児時間」にも給与を支払う旨の社内規程がない限り、いわゆるノーワーク・ノーペイの原則(労働契約法6条参照)に従い、無給となるものと考えられます。
もっとも、「育児時間」中の給与の取り扱いについては、疑義が生じることのないよう、あらかじめ就業規則(給与規程)等に定めておくことが適切です。 -
(3)「育児時間」の取得可能な時間帯
「育児時間」の取得可能な時間帯「育児時間」をどの時間に請求するかは、原則として請求権者の自由とされています。
そのため、始業時間の直後や終業時間の直前に請求を受けた場合であっても、使用者はこれを拒否できません(昭和33年6月25日基収第4317号)。
また、使用者があらかじめ一方的に「育児時間」を指定して、それ以外の時間帯での取得請求を拒否することは違法であるため、注意が必要です。 -
(4)「育児時間」の回数
「育児時間」の回数「育児時間」の原則は、1日2回、それぞれ30分以上です。
もっとも、「育児時間」を一括して一度に請求することを認めることは、分割請求や回数を制限するものでない限り、差し支えありません(昭和33年6月25日基収第4317号)。 -
(5)「育児時間」の使い方
「育児時間」の使い方前述のとおり「育児時間」はもともと授乳を念頭に置いた制度ではありますが、労働基準法67条は「育児時間」の使い方を哺育に限定していないため、使用者が時間の使い方を制限することはできません。
実務上も、「育児時間」を使い方として、保育園への送迎を行う例などがしばしば見られているところです。 -
(6)育児のための往復時間
育児のための往復時間授乳など子どもの世話のために保育園等と就業場所の間を往復する場合には、往復時間の考慮が問題となりますが、使用者は、往復時間を含んで30分以上の「育児時間」を付与していれば、違法ではないとの行政解釈が示されています(昭和25年7月22日基収第2314号)。
一方で、労働基準法67条の立法趣旨に照らして、往復時間を考慮し、実質的な育児時間を与えることが望ましいとされているところです(昭和25年7月22日基収第2314号) 。 -
(7)育児短時間勤務との併用
育児短時間勤務との併用育児休業していない3歳未満の子どもを養育する労働者が申し出たときには、使用者は、原則として、短時間勤務等の措置を講じる必要があります(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)23条1項本文)。
育児介護休業法上の育児短時間勤務の申出権者は、「育児時間」の請求権者と重なるため、「育児短時間勤務」と「育児時間」の併用の可否が問題となります。
この点、育児時間と育児短時間勤務は、「その趣旨及び目的が異なることから、それぞれ別に措置すべき」との行政解釈が示されています(平成21年12月28日職発第1228第4号・雇児発第1228第2号)。
したがって、使用者としては、「育児時間」の請求について、育児短時間勤務の対象者によるものであることを理由として拒絶することは違法となるため、注意が必要です。 -
(8)変形労働時間制における「育児時間」
変形労働時間制における「育児時間」について、変形労働時間制の適用される労働者であっても、1歳未満の子どもを育てる女性であれば、「育児時間」の請求を認めなければなりません。
さらに、「育児時間」の請求者が、労働基準法66条1項による請求(妊産婦による1日または1週間の法定労働時間を超える労働時間について労働しないことの請求)をせずに変形労働時間制の下で労働し、1日の所定労働時間が8時間を超える場合には、具体的状況に応じ法定以上の育児時間を与えることが望ましいとされています(昭和63年1月1日基発第1号・婦発第1号)。
3、「育児時間」への対応
前記FAQでみてきたとおり、法は、「育児時間」の具体的な手続については規定しておらず、労使間の個別協議に委ねています。
しかしながら、申請を受けてから慌てて場当たり的な対応するのでは混乱を招くおそれがあるため、事前にルールを定めておくこと(社内規程の整備をしておくこと)が適切です。
-
(1) 「育児時間」の申請手続
具体的には、まず、「育児時間」の申請手続について、休憩時間に準じるものとして、就業規則中の「休憩時間に関する事項」に規定しておくことが考えられます。
-
(2)「育児時間」中の給与
また、「育児時間」中の給与についても、就業規則中の「賃金に関する事項」にあらかじめ規定しておくことが適切です。
-
(3)自社独自の制度の創設を検討
さらに、子育て中の有能な従業員の繋留策等として、「育児時間」対象者の男性労働者への拡大や、哺育対象の子どもの年齢の引き上げなど、自社独自の制度を創設することも考えうるところです。
問題社員のトラブルから、
4、まとめ
「育児時間」は比較的馴染みの薄い制度ですが、適法な申請を拒絶した場合は労働基準法違反として刑事罰を科されるおそれがあるため、事業主や企業の人事担当者の方には、「育児時間」に関する十分な理解が必要です。
また、「育児時間」の具体的な運用については、各社の判断に委ねられているため、社内規程の整備を図る必要があります。適法性を確保しながら、自社の実情に即した態勢整備を実現する上では、労働法務に通じた弁護士等専門家を活用することもご検討いただければと思います。
ベリーベスト法律事務所では、実務に精通した弁護士が労働法務部門の支援に積極的に取り組んでおりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- 内容・ご事情によりご相談をお受けできない可能性もございます。
- ご相談者様が、法人格のない個人事業主様の場合、初回相談は有料となります。
同じカテゴリのコラム
-

減給は10分の1までしかできない? 減給の上限をケース別に解説
2025年06月30日- 労働問題
企業では従業員の不祥事や職務懈怠、能力不足、あるいは会社の業績不振など、様々な理由で従業員の減給を検討することがありますが、無制限に減給できるものではありません。減給の方法によっては、法律で「10分…
- 減給
- 10分の1
-

転勤を拒否する従業員を解雇できる? 解雇以外の正しい対処法も解説
2025年06月26日- 労働問題
会社が転勤を命じたにもかかわらず、従業員が転勤を拒否するケースも珍しくはありません。従業員にも諸事情はあるでしょうが、会社としては業務上の必要性から転勤を命じているのですから、従業員の個人的な都合を…
- 転勤
- 拒否
- 従業員
- 解雇
-

労務管理とは? ずさんだとヤバい? 人事・労務管理者の基礎知識
2025年06月23日- 労働問題
「労務管理」とは、従業員のさまざまな事項全般を管理する業務です。適切な労務管理ができていない企業では、労働者が気持ちよく働くことができません。そのため、生産性の低下や離職者の増加などにつながるリスク…
- 労務管理とは
企業法務コラム
- 企業法務・顧問弁護専門サイト
- 企業法務コラム
- 労働問題
- 育児時間とは? 従業員から申請される前に会社が確認しておくべき基本的事項
お問い合わせ・資料請求