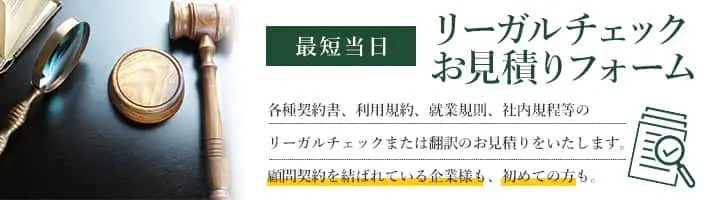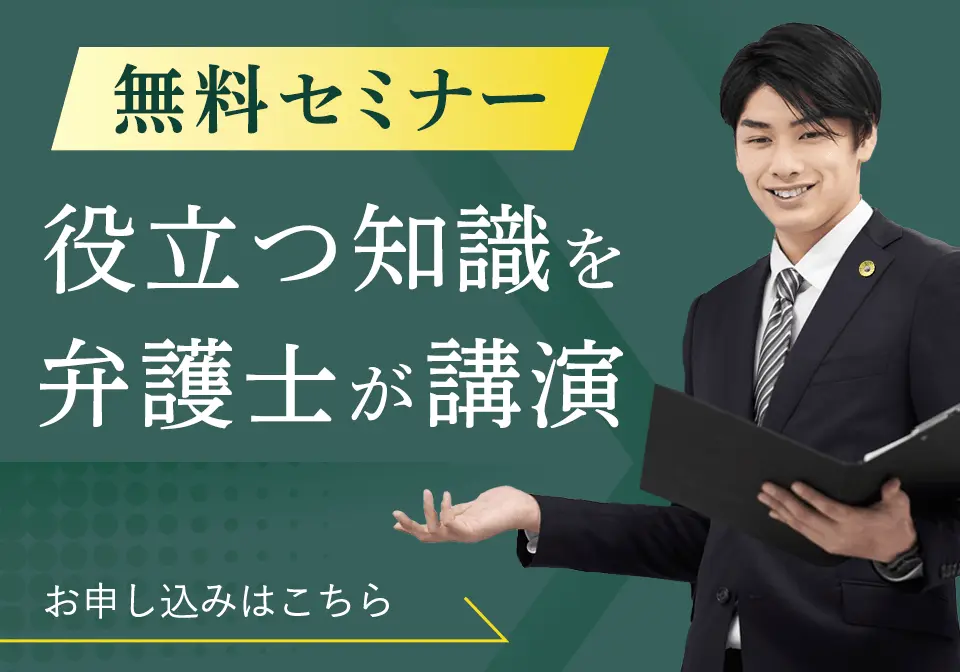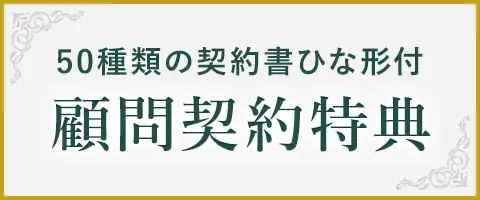- 企業法務・顧問弁護専門サイト
- 企業法務コラム
- 労働問題
- 飲み会に強制参加させると残業代が必要? 企業が知っておくべき注意点
飲み会に強制参加させると残業代が必要? 企業が知っておくべき注意点

日本企業の伝統ともいえる「飲みニケーション」。たしかに飲み会はコミュニケーションの活性化を図るうえで、有効な手段のひとつと考えられています。
しかし、飲み会を敬遠する人が若年層の労働者を中心に増えているといわれるなか、飲み会への参加を強制することによって残業代を請求される、ブラック企業との風説を流布されるとなどのケースもあります。なかには、社内文化としての飲み会を嫌い、転職を希望する労働者も存在するようです。
そこで、本コラムでは労働者である社員に対して、飲み会への参加を強制することが企業にとって法的にどのような意味をもつか、企業が飲み会への強制参加に対するリーガルリスクを最小化すると同時に、労働者間のコミュニケーションを活性化するために考えられる方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、企業が知っておきたい、労働時間・残業時間の定義
強制的に飲み会に参加させることが、企業にとって法的にどのような意味をもつのか、残業代の支払い義務が生じるのかを説明する前に、まずは基本的な労働時間、残業の定義を知っておきましょう。
-
(1)労働時間の定義
労働基準法第32条第1項では、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて労働させてはならない」という、いわゆる「週40時間制の原則」を規定しています。
ここでいう「労働時間」とは、一般的に「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことをいいます。 -
(2)残業時間の定義
労働時間として1日8時間を超える時間外労働(残業)を労働者に課す場合、まずは労働基準法第36条第1項に定める時間外・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)を労働組合など労働者の代表と締結することと、所轄労働基準監督署への届け出が必要です。
もっとも、36協定を締結しているからといって、企業は労働者に対して無制限に時間外労働を課すことができるわけではありません。
2019年4月1日から施行された一連の「働き方改革関連法」では、時間外労働および休日労働に対して以下の上限を設けています(中小企業は2020年4月1日より施行)。● 残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない。
● 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできない。
- ① 1年720時間以内
- ② 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内 - ③ 月100時間未満 休日労働を含む
- ④ 原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで
-
(3)残業時間の種類と割増率
なお、労働者の時間外労働をした場合、企業は労働者に「残業代」を支払う義務があります。残業代は、大きく分けて以下の4パターンがあります。
① 法定内残業
たとえば、就業規則や雇用契約で1日の所定労働時間が7時間だった場合、法定労働時間よりも労働時間は短くなります。このケースにおいて労働時間が8時間となった場合に、差分の1時間に対して支払われるべき残業代のことです。
この場合の残業代は基礎賃金と同額であり、就業規則等で特に定めがない限り、割増しはありません。
② 法定外残業
1日8時間・週40時間の法定労働時間を超える労働を法定外残業といい、基礎賃金に25%を付加した残業代を支払う義務があります(労働基準法第37条第1項)。
③ 深夜労働
労働者が午後10時から午前5時までの時間帯に労働した場合、深夜労働に該当します。
深夜労働に対する割増率も25%です(労働基準法第37条第4項)。
④ 法定休日労働
労働基準法では、使用者は労働者に対して原則1週間あたり1日以上の休日を与えることが規定されており(労働基準法第35条第1項)、これを法定休日といいます。
この法定休日に労働者に対して労働を命じた場合、企業は割増率35%の賃金を支払うことが義務付けられています(労働基準法第37条第1項)。
2、飲み会が「労働時間」とみなされるかは「強制参加」か「任意参加」かによって異なる
-
(1)「強制参加」であれば、労働時間とみなされる可能性がある
企業の飲み会が労働時間にあたるのか否かは、企業が労働者に対して「業務として参加を命じたかどうか」ということがポイントになります。
先述のとおり、労働時間の定義は「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。したがって、通常業務とは関係のない飲み会であろうと、その参加を使用者として労働者に強制した場合、労働者は使用者の指揮命令下に置かれていることになり、飲み会は労働者にとって労働時間となるのです。 -
(2)飲み会の時間に対して、残業代の支払いが必要になる可能性も
飲み会が業務に付随する仕事として労働時間に該当すると認められると、労働者が飲み会に参加した時間に対して、企業は残業代を支払う必要があるとみなされる可能性があります。
飲み会にかぎらず、社内旅行などの社内行事についても参加が強制された場合は同様です。
3、どのようなケースが「強制参加」とみなされるのか
-
(1)強制参加と判断されうるケース
飲み会への参加が強制とみなされるケースは、参加についての直接的・間接的な働きかけを問いません。
たとえば、次のようなケースが該当すると考えられます。- 上司が飲み会への参加を、業務命令であると明言している。
- 名目上は自由参加とされているが、参加しないと回答したことで当該労働者が給与の減額や降格など人事上の不利益を被る。
- 飲み会に参加しないことで、職場の人間関係から切り離されたり仕事を進めるうえでの不利益を被ったり、上司からしっ責(パワハラ)される。
- 業務命令として飲み会の幹事に指名することで、任意で欠席できないようにする。
-
(2)任意参加と判断されうるケース
上記を踏まえると、飲み会はあくまで有志によるもので、出席・欠席を自由に選択でき、欠席することで労働者に何らの不利益は生じないとすることにより、当該飲み会が任意参加によるものとすることができます。
-
(3)飲み会以外でも、労働時間として認められる可能性がある行事
たとえば取引先との親睦を深めるための接待やゴルフは、営業行為のひとつとして労働時間として認められる可能性があります。
また、社内行事でもある社員旅行への参加や、近年話題に上ることの多いお花見の場所とりなどを命じた場合も、労働時間として認められる可能性があるでしょう。
飲食やゴルフのプレーをしている時間そのものが業務にあたるのかという点は、さまざまな見解がありますが、明確に「業務として命じたかどうか」が労働時間として認められる分岐点であると考えられます。
問題社員のトラブルから、
4、強制的に飲み会へ参加させると違法になる?
-
(1)業務であると考えられる場合
飲み会を業務の一環として規定することは可能ですし、実際に飲み会への参加を業務の一環としている企業も存在するようです。
飲み会への参加を業務の一環と定義すれば、残業代を支払うことを前提に労働者に対して飲み会を命じることも可能と考えられます。 なぜなら、労働者は雇用契約や就業規則に従い企業に対して労働力を提供する義務があるからです。これを正当な理由なく拒否することは、企業に対する業務命令違反と考えられます。
しかし、法定残業時間を超えるほどの長時間の飲み会や、労働者の心身に影響がでるほどの頻度や長時間で行われる飲み会への参加を強制すると、企業は安全配慮義務違反に問われる可能性があります(労働契約法第5条)。
また、飲み会への参加を拒否する労働者に対して、暴力やどう喝などをもちいて無理に強制すると、「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」と規定する労働基準法 第5条に違反する可能性があります。 -
(2)業務外の場合
飲み会が契約上業務の内容に含まれていない場合や、残業代が支払われない業務外の飲み会の場合には、飲み会に労働者を強制的に参加させることは認められません。
たとえ企業が、飲み会の費用を全額負担していたとしても同様です。
業務外、つまり労働者にとって休息をとるためのプライベートな時間に、飲み会への参加を強制することはできないのです。
労働者が断っているにもかかわらず無理やり誘い続ける、参加しないことに対して暴言を吐くなどの行為があると、パワハラやセクハラで訴えられる可能性があることも覚えておく必要があります。
5、飲み会トラブルを起こさないために、企業としてできること
飲み会への強制参加に関するトラブルを防ぐためには、企業として以下のよう対策をしてくことが望ましいと考えられます。
-
(1)労働者のモラルを教育する(飲みニケーションは通じない)
世代によっては、飲み会への参加を当たり前と考える労働者も存在すると考えられます。
そのような労働者は、飲み会への参加を拒否する労働者と意識の乖離(かいり)があるものです。特に上司になった場合、部下とのひずみが生まれる可能性が大きくなります。
したがって、なぜ飲み会への参加を強制することが企業にとって不利益なのか、法的見地を交えた研修を行うことで、トラブルの芽を事前に摘むことが大切です。 -
(2)勤務外の飲み会であれば、強制ととられないように配慮する
先述したように、飲み会への参加は強制ではなく、あくまで有志によるものであると広く労働者に認知させることが重要です。もちろん、飲み会への不参加による人事上の不利益などがあってはなりません。
-
(3)業務時間外の飲み会以外を検討する
業務時間終了後の飲み会以外に、ランチタイムや通常業務の終了時間を繰り上げたうえでの親睦会や飲み会を検討するのも一案でしょう。
ただし、ランチタイムに親睦会を実施する場合は、ランチタイムつまり休憩時間を労働者の「自由に利用させなければならない」と規定した労働基準法第34条第3項の規定、および休憩時間が「労働者の権利として労働から離れることを保障された時間」であるという労働基準法施行時の通達に反する可能性があることを十分に考慮しておく必要があります。 -
(4)就業規則に飲み会に関する規定を盛り込む
飲み会参加に付随して、交通費や会費などが問題になることも少なくありません。そういった点は、労働契約や就業規則などに規定しておくことが有効でしょう。
企業としての考えやルールをあらかじめ労働者に広く周知しておくことで、無用なトラブルになることを避けられます。
問題社員のトラブルから、
6、まとめ
これまでご説明したように、労働者に対する飲み会参加の強制は、時代の変化に伴い非常にセンシティブなテーマになりつつあります。
また、ドラマで取り上げられたことや、インターネットやSNSで気軽に情報が収集できるようになったこともあり、労働者側が声をあげやすくなっている社会の情勢も、企業としては意識しておくべきでしょう。
労働者とのトラブルを未然に防ぎ、労働基準法など各種法令リスクの極小化を図るうえでは、弁護士などの専門家によるリーガルオピニオンが欠かせません。
飲み会にまつわるトラブルを抱えてお困りの場合は、労働問題や企業法務の対応実績が豊富な、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
貴社のために、ベストを尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- 内容・ご事情によりご相談をお受けできない可能性もございます。
- ご相談者様が、法人格のない個人事業主様の場合、初回相談は有料となります。
同じカテゴリのコラム
-

減給は10分の1までしかできない? 減給の上限をケース別に解説
2025年06月30日- 労働問題
企業では従業員の不祥事や職務懈怠、能力不足、あるいは会社の業績不振など、様々な理由で従業員の減給を検討することがありますが、無制限に減給できるものではありません。減給の方法によっては、法律で「10分…
- 減給
- 10分の1
-

転勤を拒否する従業員を解雇できる? 解雇以外の正しい対処法も解説
2025年06月26日- 労働問題
会社が転勤を命じたにもかかわらず、従業員が転勤を拒否するケースも珍しくはありません。従業員にも諸事情はあるでしょうが、会社としては業務上の必要性から転勤を命じているのですから、従業員の個人的な都合を…
- 転勤
- 拒否
- 従業員
- 解雇
-

労務管理とは? ずさんだとヤバい? 人事・労務管理者の基礎知識
2025年06月23日- 労働問題
「労務管理」とは、従業員のさまざまな事項全般を管理する業務です。適切な労務管理ができていない企業では、労働者が気持ちよく働くことができません。そのため、生産性の低下や離職者の増加などにつながるリスク…
- 労務管理とは
企業法務コラム
- 企業法務・顧問弁護専門サイト
- 企業法務コラム
- 労働問題
- 飲み会に強制参加させると残業代が必要? 企業が知っておくべき注意点
お問い合わせ・資料請求