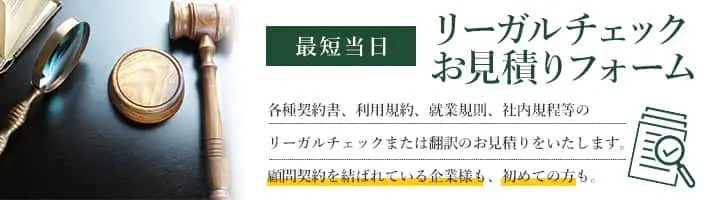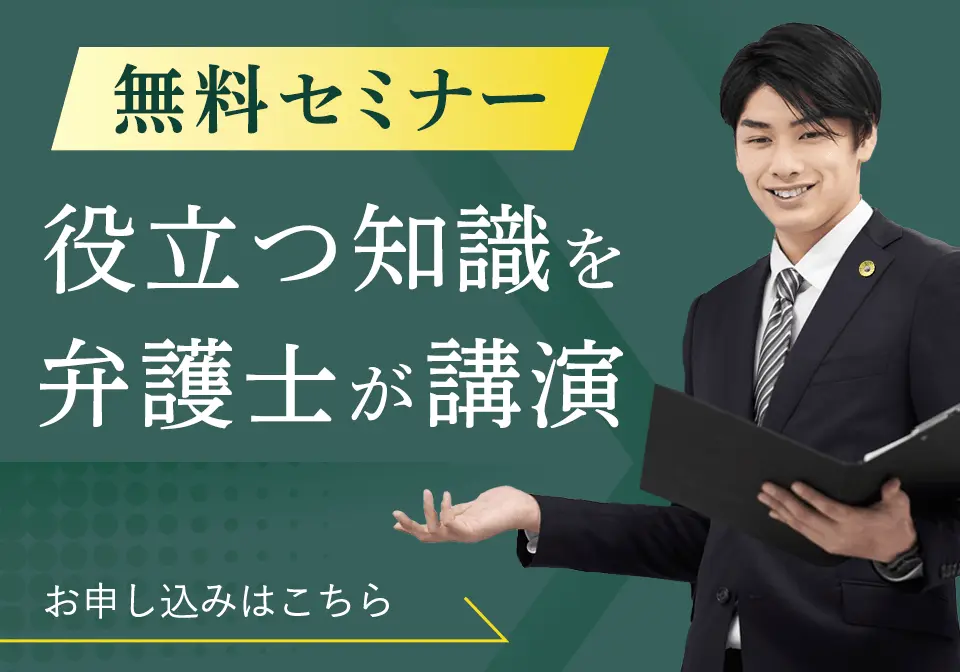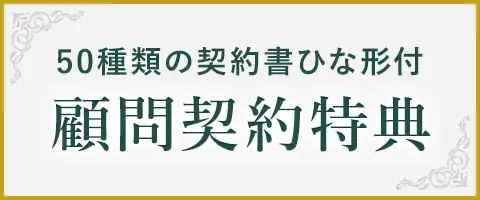- 企業法務・顧問弁護専門サイト
- 企業法務コラム
- 労働問題
- 引き継ぎもせず突然の退職! 会社から従業員に損害賠償請求は可能?
引き継ぎもせず突然の退職! 会社から従業員に損害賠償請求は可能?

人手不足が深刻化する昨今、労働者の突然の退職により大きな損失を受ける会社も多いと考えられます。なかには、引き継ぎもせず突然退職するような労働者に対して、損害賠償を請求したいと考える経営者もいることでしょう。
しかし、労働基準法などの各種法令は労働者の権利を守るためのものであり、退職した労働者に対して会社が損害賠償請求をできるケースはかぎられているのです。
そこで本コラムでは、退職した労働者に対して会社が損害賠償を請求できるケース・できないケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、法律上における退職のルール
憲法第22条1項では「職業選択の自由」が定められており、労働者に対して転職や退職の自由を認めています。
一方で民法では、期間の定めのない雇用契約と、期間の定めのある雇用契約で労働者が自発的に退職できる基準を設けています。
それぞれについて確認していきましょう。
-
(1)期間の定めのない雇用契約(無期雇用)の場合
民法627条第1項では、会社と期間の定めのない雇用契約を締結している労働者に対して、退職の日から2週間前までに会社へ申し入れれば退職できると規定しています。
-
(2)期間の定めのある雇用契約(有期雇用)の場合
労働者が会社と期間の定めのある雇用契約を締結している場合、原則としてやむを得ない事由がなければ雇用契約を解除することはできません(民法第628条)。
ただし、労働基準法第137条では、契約期間の初日から1年を経過した日以降においては、労働者は使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます。
なお、(1)、(2)いずれの場合においても、使用者から明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を解除できます(労働基準法第15条1項、2項)。
問題社員のトラブルから、
2、退職する従業員に損害賠償請求をできる可能性があるケース
-
(1)有期雇用で期間内に一方的に退職してしまった場合
民法第628条の規定により、有期雇用の期間内であってもやむを得ない事由がある場合は、会社および労働者は契約の即時解除、すなわち退職することができます。
ただし、退職する理由が会社または労働者の一方の過失によるものであるときは、会社または労働者は相手方に対して損害賠償を請求できると規定されています。 -
(2)引き継ぎをせず退職した場合
労働者が退職するとき、後任に対して業務の引き継ぎを行うことは、会社に対する信義則上の義務であると考えられています。
したがって、労働者が後任に対して一切の引き継ぎを行わず退職し、業務に損害をもたらした場合、会社は当該労働者に対して損害賠償請求をできる可能性が高くなります。 -
(3)退職するとき、他の従業員に転職の勧誘や引き抜きをした場合
会社に在職しているかぎり、労働者には会社にとって不利益なことをしてはならないという「誠実義務」や「競業避止義務」が課せられます。
したがって、退職前に他の従業員に転職の勧誘や引き抜きという不法行為をした労働者に対して、会社は損害賠償を請求できる可能性があります。
もっとも、引き抜きにより退職する労働者にも退職の自由がある以上、引き抜きを行った労働者の行為が、通常の勧誘行為にとどまる限りは適法であると考えられます。
したがって、労働者の引き抜き行為についての損害賠償請求は、競合他社と労働者が共謀の上、会社の従業員を一斉に大量に転職させるなど、悪質性の高い事例であれば認められる可能性が高くなるといえるでしょう。 -
(4)研修・留学を経験後、短期間で辞めた場合
労働基準法第16条では、会社に対して
労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない
と規定しています。
では、会社が多額の費用を負担し研修や留学を経験させたあとに短期間で労働者が退職してしまった場合は、どうなのでしょうか。
過去の裁判例をみると、研修や留学に際し、労働者が「〇年以内に退職した場合は会社に研修費用相当額を支払います」というような誓約書を差し入れていた場合であっても、実際に会社が退職した労働者に対して請求できるポイント、つまり労働基準法第16条に該当しないとされたケースは、当該研修や留学が「労働者にとっての利益が強く、業務性が薄い」場合であるとしています。
この場合、会社が支払った研修や留学の費用は、労働者に対する貸付金(立替金)とその返済期間の猶予と解され、会社はかかった費用を労働者に対し請求できる可能性があります。 -
(5)入社後、すぐに退職した場合
特定の業務を担当するために採用した労働者が早期に退職し、それにより会社が逸失利益などの損害を被ってしまったケースで、労働者に対する損害賠償請求が認められた裁判例が存在します。
この事例は、新規事業立ち上げのために雇用された労働者が、わずか4日間で退職した事案であり、会社から労働者に対する200万円の請求に対し、70万円の限度で損害賠償請求が認められました。
これは、労働者が退職したことで、会社の労働者に対する給与や経費の支払いを免れたこと等を理由に、認容額は70万円にまで減額されたものと考えられます。 -
(6)無断欠勤により出社を拒否する場合
先述した民法第627条および第628条の規定により、雇用期間の定めがない場合は退職の意思を表示したあとの2週間を経過するまで、雇用期間の定めがある場合は雇用期間満了またはやむを得ない事情がある場合を除いて、労働者は退職することができません。
つまり、退職するまでの間は会社と労働契約が存在しているわけですから、会社に対して労働者は誠実に労働する義務を負っているのです。
したがって、退職できないからといって労働者が無断欠勤により出社を拒否することは、労働者による債務不履行であり、それに対して会社は損害賠償を請求できる可能性があります。
もっとも、実務上、労働者が退職の意思表示をした後、2週間残存していた有給休暇を消化して事実上出社しない場合が多いです。
この点、有給休暇の消化については労働基準法第39条第5項の規定により、会社の事業の正常な運営を妨げる場合は、会社が労働者に対して有給休暇の取得時季を変更させることができる「時季変更権」が認められているものの、当然ながら退職日を超える時季変更はできませんので、退職の意思表示をした労働者に時季変更権を行使できる場合は少ないものと考えられます。
したがって、事実上、出社を拒否している場合に損害賠償請求できるケースはかなり限定されます。 -
(7)何らかのトラブルを起こし、そのまま出社せず退職した場合
労働者の責めに起因するトラブルにより会社に損害が発生した場合、基本的に会社は当該労働者に対して損害賠償を請求できると考えられます。これは当該労働者が退職した場合であっても同様です。
ただし、トラブルや会社が被った損害が労働者の責めに起因するものであっても、そのトラブルや損害が会社の指揮命令のもと生じたものである場合は、「責任制限の法理」により会社の損害賠償請求が100%認められることは難しく、裁判例上も2分の1から4分の1の範囲で認められることが多いようです。
会社が労働者に対し、いくらの損害賠償請求が可能かは、労働者の帰責性の程度や労働者の地位・職務内容・労働条件に加えて、損害発生の寄与度を考慮します。
3、退職の際、損害賠償請求が難しいケース
会社の退職する労働者に対する損害賠償請求が認められるためには、以下の3点が重要であると考えられます。
- 労働者の退職について、労働者側に故意又は過失による加害行為があること。
- 上記により、会社に重大な損害が発生していること。
- 労働者の故意又は過失による加害行為の存在や当該加害行為によって会社に損害が発生したことにつき、会社側が客観的に立証できること。
つまり、上記の点が整っていない場合、退職した労働者に対して会社が損害賠償を請求することは基本的に難しいと考えられます。
4、就業規則の規定より早く退職したいという申し入れは拒否できる?
会社が就業規則で「退職する日の3か月前に会社に申請すること」と規定しているのにもかかわらず、労働者が「期間の定めのない雇用契約の場合であれば、退職の申し入れの日から2週間を経過していれば退職できる」という民法第627条の規定を根拠に、退職日まで未消化の有給休暇を取得したうえで退職を強行しようとした場合、申し出を拒否することはできるのでしょうか。
結論からいいますと、当該労働者の申し入れを拒否することは基本的に難しいでしょう。
民法や労働基準法の規定は、就業規則に優先されます。民法第627条の規定は、判例や学説でも「強行規定」なのか「任意規定」なのか見解が分かれているものの、退職の意思表示後2週間を経過することで、民法上労働者は退職できると解されます。
また、会社が後任者を雇い入れるために必要最小限の期間、退職を待ってほしいという場合であっても、それは会社の都合であって労働者の退職意思を拒否する理由にはなりません。
したがって、退職日についてどうしても労働者と折り合いがつかない場合は、弁護士などの第三者を交えて労働者と話し合うことも一案です。
5、注意! 退職する従業員から逆に損害賠償請求される可能性も
労働者の退職により被った損害を請求しようとしても、以下のような行為が会社に認められた場合は、逆に労働者側から損害賠償請求または未払賃金支払請求をされる可能性があります。
- 未払いの給与や残業代がある
- 退職金規定があるにもかかわらず、退職金を支払わない
- 離職票を出さない
- 正当な理由なく、有給休暇の消化を認めない
- 退職を希望する労働者に「懲戒解雇にする」「退職するのであれば損害賠償請求をする」などと脅した
上記のような行為は、労働基準法などの法令にも違反します。
その結果、会社は労働者からの損害賠償請求だけでなく行政上・刑事上の処分を受ける可能性もあるため、注意が必要です。
問題社員のトラブルから、
6、まとめ
多くの会社にとって、労働者の突然の退職は損失です。
しかし、労働者としては新しいスタートを一日でも早く切りたいと考えているため、退職を希望する労働者と会社がトラブルになることも少なくありません。
退職の意思表示をした労働者と十分な話し合いができない場合、あるいは労働者の突然の退職によりトラブルになった場合、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士であれば会社の代理人として、労働者と交渉することが可能です。
また、退職をめぐるトラブルを予防するうえでは、引き継ぎすら行わず突然退職するような労働者が出ないような体制づくりをすることも重要です。
この点についても、弁護士は就業規則や社内体制を整えるための助言が可能です。
ベリーベスト法律事務所では、顧問弁護士サービスを提供しています。
労働者の退職に関してトラブルを抱えている場合や、顧問弁護士の導入を検討されている場合は、ぜひお近くのベリーベスト法律事務所の弁護士までご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- 内容・ご事情によりご相談をお受けできない可能性もございます。
- ご相談者様が、法人格のない個人事業主様の場合、初回相談は有料となります。
同じカテゴリのコラム
-

減給は10分の1までしかできない? 減給の上限をケース別に解説
2025年06月30日- 労働問題
企業では従業員の不祥事や職務懈怠、能力不足、あるいは会社の業績不振など、様々な理由で従業員の減給を検討することがありますが、無制限に減給できるものではありません。減給の方法によっては、法律で「10分…
- 減給
- 10分の1
-

転勤を拒否する従業員を解雇できる? 解雇以外の正しい対処法も解説
2025年06月26日- 労働問題
会社が転勤を命じたにもかかわらず、従業員が転勤を拒否するケースも珍しくはありません。従業員にも諸事情はあるでしょうが、会社としては業務上の必要性から転勤を命じているのですから、従業員の個人的な都合を…
- 転勤
- 拒否
- 従業員
- 解雇
-

労務管理とは? ずさんだとヤバい? 人事・労務管理者の基礎知識
2025年06月23日- 労働問題
「労務管理」とは、従業員のさまざまな事項全般を管理する業務です。適切な労務管理ができていない企業では、労働者が気持ちよく働くことができません。そのため、生産性の低下や離職者の増加などにつながるリスク…
- 労務管理とは
企業法務コラム
- 企業法務・顧問弁護専門サイト
- 企業法務コラム
- 労働問題
- 引き継ぎもせず突然の退職! 会社から従業員に損害賠償請求は可能?
お問い合わせ・資料請求