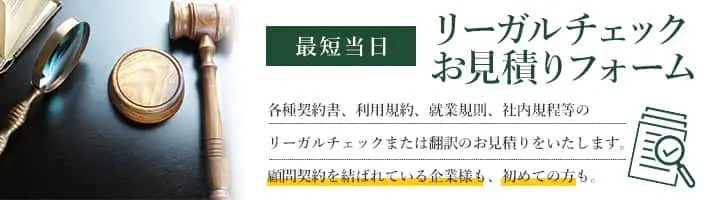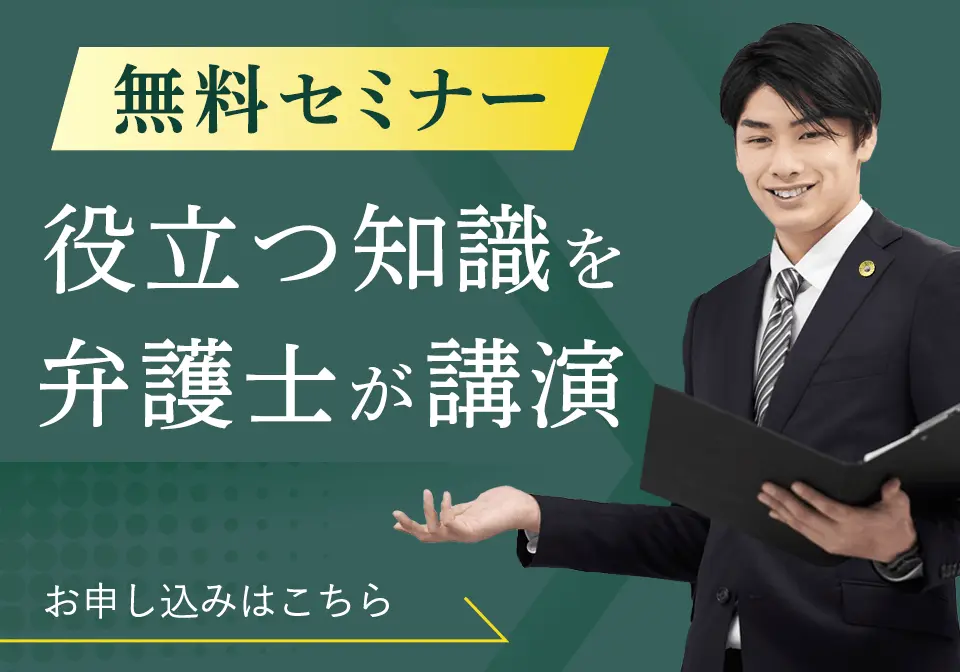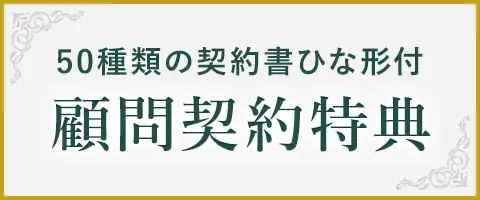- 企業法務・顧問弁護専門サイト
- 企業法務コラム
- 労働問題
- バックペイとは? 不当解雇で訴えられた企業の義務とリスク
バックペイとは? 不当解雇で訴えられた企業の義務とリスク

会社(使用者)が従業員を解雇した場合、従業員から解雇の有効性を争われる可能性があります。また、この場合、同時にバックペイの請求を受けることがほとんどです。
解雇に関する問題が長引けば長引くほど、バックペイが積み重なって高額になってしまう可能性があります。そのため、会社がバックペイを請求された場合、すみやかに争いを解決することが重要です。
会社の負うリスクや損害を最小限に抑えるためには、弁護士への相談により、従業員の主張の妥当性を検証することが不可欠です。本コラムでは、企業の経営者が知っておくべき「バックペイ」の概要や注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
1、バックペイとは?
バックペイとは、従業員の解雇が無効となった場合に、会社が支払わなければならない未払賃金を意味します。
会社が従業員を有効に解雇した場合、雇用契約は終了し、解雇日以降の賃金を支払う必要はありません。
しかし、解雇が無効だった場合、会社と従業員の雇用契約は存続していることになります。
そのような場合、会社は解雇日以降に未払いになっていた賃金を支払わなくてはいけません。このとき、会社が従業員に支払わなければならない未払賃金を「バックペイ」といいます。
バックペイは、争いが長引けば長引くほど高額になるため、解雇の有効性を巡る紛争において重要な論点になることが多々あります。
問題社員のトラブルから、
2、バックペイを支払うのは企業の義務?
-
(1)解雇から1度も出勤していない従業員にもバックペイは必要か?
解雇が無効となった場合、会社は、従業員に対してバックペイを支払う義務を負います。
ところで、解雇された従業員は、解雇日以降は会社へ立入ることができなくなるのが一般的です。解雇されてから出勤していない従業員に対してもバックペイを支払う必要があるのでしょうか。
民法では、債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったとき、債権者は、反対給付の履行を拒むことができないとされています(民法第536条2項前段)。
一般的に従業員は業務を行わなければ給与を受け取ることはできません。
しかし、会社側の事情(=債権者の責めに帰すべき事由)で従業員が業務を行えなかった場合には、業務の対価である給与の支払い(=反対給付の履行)を拒むことができないのです。
解雇を理由に従業員が会社に立ち入ることを禁止していた場合、実は解雇が無効だったということになってしまうと、従業員が業務をできなかったのは、会社に責任であり、給与は支払わなければならないということになってしまいます。 -
(2)解雇が違法・無効となる場合の判断基準
解雇が違法・無効となるのは、以下のような、解雇の種類に応じた要件を満たしていない場合です。
普通解雇の要件- ① 労働契約上の解雇事由に該当すること
- ② 解雇に客観的・合理的な理由があり、社会通念上相当であること
整理解雇の要件
以下の4つの観点を総合的に考慮して、解雇に客観的・合理的な理由があり、社会通念上相当であること(整理解雇の4要件)
- ① 経営破綻の危機にあるなど、整理解雇を行う高度の必要性があること(整理解雇の必要性)
- ② 他の手段を尽くしてもなお、整理解雇が真にやむを得ないこと(解雇回避努力義務の履行)
- ③ 整理解雇の対象者が、適切な基準に基づき、当該基準を合理的・公平に適用して選定されたこと(被解雇者選定の合理性)
- ④ 労働者側に対して、整理解雇についての説明・協議などを尽くしたこと(手続きの妥当性)
懲戒解雇の要件- ① 就業規則上の懲戒事由に該当すること
- ② 解雇に客観的・合理的な理由があり、社会通念上相当であること
上記のように、「解雇に客観的・合理的な理由があり、社会通念上相当であること」はすべての解雇に共通する要件となっています。
これは「解雇権濫用の法理」(労働契約法第16条)に由来するものです。
形式的には懲戒事由や解雇事由に該当するものの、「解雇に客観的・合理的な理由があり、社会通念上相当であること」が認められず、解雇が無効になってしまうという例はよくみられます。
3、バックペイの計算方法
バックペイの金額は、原則として、解雇がなければ確実に従業員に支払われたであろう賃金の額です。
例外的に、従業員化が解雇されてから別の仕事をして収入を得ていた場合には、その収入の金額を解雇がなければ支払われたであろう金額から控除します(民法536条2項後段)。ただし、解雇日直前の平均賃金の金額の6割は最低限支払わなければいけません。(労働基準法第26条)。
平均賃金は労働基準法第26条に定められた方法で計算します。
過去3か月間の賃金を単純に平均した額ではないことには注意が必要です。
以下では、設例を用いながら、バックペイの計算方法を解説します。
-
(1)解雇期間中の収入がない場合のバックペイ
設例 ①- 2022年5月31日に解雇された
- 給与は額面で月額30万円、月末締め翌月25日払い
- 解雇が無効となり、2022年9月1日から復職した
- 2022年6月1日から2022年8月31日までの期間中は無職だった
この場合、バックペイの金額は、90万円となります。
解説
設例①では、2022年5月31日に解雇されています。
給与は月額30万円、給与が支払われなかった期間は3か月なので、解雇がなければ支払われたであろう金額は90万円(=30万円×3か月)となります。 -
(2)解雇期間中に中間収入があった場合のバックペイ
設例 ②- 2022年5月31日に解雇された
- 給与は額面で月額30万円、月末締め翌月25日払い
- 解雇直前の平均賃金は日額1万円
- 解雇が無効となり、2022年9月1日から復職した
- 2022年6月1日から2022年8月31日までの期間中に別の会社で働いて、総額70万円の賃金を受け取っていた
この場合、バックペイの金額は55万2000円となります。
解説
設例②の条件は、設例①とほとんど同じですが、2022年6月1日から2022年8月31日までの期間中に別の会社で働いて、総額70万円の賃金を受け取っていたという点が異なっています。
この場合、バックペイの計算は、設例①よりも少々複雑になります。
解雇がなければ支払われたであろう賃金の額は、設例①同様、90万円です。
解雇されてから復職するまでの期間(92日間)の平均賃金は92万円あり(平均賃金日額1万円×92日)、この6割の金額は55万2000円です。
解雇がなければ支払われたであろう賃金の額から、従業員が他の会社から受け取っていた賃金を差し引くと、20万円(=90万円-70万円)となります。これは、上記55万2000円を下回る金額になります。
このため、設例②では、バックペイの金額は55万2000円となります。設例 ③- 2022年5月31日に解雇された
- 給与は額面で月額30万円、月末締め翌月25日払い
- 解雇直前の平均賃金は日額1万円
- 解雇が無効となり、2022年9月1日から復職した
- 2022年6月1日から2022年8月31日までの期間中にアルバイトをして、総額10万円の賃金を受け取っていた
この場合、バックペイの金額は80万円となります。
解説
設例③では、2022年6月1日から2022年8月31日までの期間中にアルバイトをして受け取った賃金が、総額10万円である点が設例②と異なっています。
解雇がなければ支払われたであろう賃金の額は、設例①同様、90万円です。
解雇されてから復職するまでの期間(92日間)の平均賃金は92万円あり(平均賃金日額1万円×92日)、この6割の金額は55万2000円です。
解雇がなければ支払われたであろう賃金の額から、従業員が他の会社から受け取っていた賃金を差し引くと、80万円(=90万円-70万円)となります。これは、上記55万2000円を上回る金額です。
このため、バックペイの金額は80万円となります。
4、失業手当はバックペイから控除されるのか?
法律上、雇用保険から給付される手当(失業手当)の金額をバックペイから控除することはできません。
損害賠償の性質を持つバックペイとは異なり、失業手当は、社会政策上の理由から、退職の理由を問わず支給されるものであるためです。
5、バックペイとは別に、損害賠償(慰謝料)の支払いは必要か?
解雇が無効になった場合でも、バックペイの他に慰謝料を支払う必要があることは稀です。
解雇によって従業員が被った精神的苦痛への賠償は、原則として、バックペイが支払われることで十分であると考えられています(東京地裁平成15年7月7日判決)。
ただし、不当解雇に伴ってパワハラなどの不法行為が行われていた場合には、バックペイの支払いのみでは賠償が不十分だと判断され、別途、慰謝料の支払義務も負う可能性があります。
なお、バックペイの支払いが訴訟で争われた場合、裁判所は、会社に対して、バックペイと同額の付加金の支払いを命ずることができます(労働基準法第114条)。
付加金が課された場合、会社にとっては倍額のバックペイを支払うことになるため、金銭的な負担が非常に重くなってしまいます。
ただし、控訴した上で、控訴審の口頭弁論の終結時までにバックペイを支払えば、付加金の支払いが命じられることはありません(最高裁平成26年3月6日判決)。
バックペイに関して従業員と訴訟になった場合には、裁判所が開示する心証をふまえると会社としては早めにバックペイを支払ってしまったほうがよい、というケースも少なくありません。
6、バックペイの支払いが認められた裁判例
近年の裁判例を参照すると、東京高裁平成31年3月14日判決において、1300万円余りのバックペイの支払いが命じられています。
1300万円余りのバックペイの支払いを命ずる判決は、会社にとって非常に負担の重い内容といえます。
企業の経営者や担当者の方は、従業員を解雇する際には、このような高額のバックペイの支払いを命じられるリスクが含まれていることも認識しておく必要があります。
7、従業員からバックペイを請求されたら弁護士にご相談を
従業員から不当解雇のバックペイを請求された場合、会社としては従業員側の主張の当否を慎重に検討したうえで、適切な対応方針を決定することが重要です。
弁護士であれば、会社が被る損失を最小限に抑えるために、解雇の有効性やバックペイの支払いに関して適切に検討・判断を行うことができます。
また、従業員との協議や法的手続きへの対応も、弁護士なら代行できます。
不当解雇を巡って従業員との間でトラブルが起こった場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
問題社員のトラブルから、
8、まとめ
従業員からバックペイの請求を受けたら、早い段階から適切な対処をしなければ、会社にとって深刻な事態に発展するおそれがあります。
バックペイを支払うのみならず、従業員の復職や付加金の支払いなど、さまざまなリスクも負うことになってしまうためです。
会社の損失を最小限に抑えるために、まずは弁護士に相談してください。
ベリーベスト法律事務所では、解雇に関して従業員との間に起こったトラブルやその他の労働問題について、企業からのご相談を承っております。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- 内容・ご事情によりご相談をお受けできない可能性もございます。
- ご相談者様が、法人格のない個人事業主様の場合、初回相談は有料となります。
同じカテゴリのコラム
-

減給は10分の1までしかできない? 減給の上限をケース別に解説
2025年06月30日- 労働問題
企業では従業員の不祥事や職務懈怠、能力不足、あるいは会社の業績不振など、様々な理由で従業員の減給を検討することがありますが、無制限に減給できるものではありません。減給の方法によっては、法律で「10分…
- 減給
- 10分の1
-

転勤を拒否する従業員を解雇できる? 解雇以外の正しい対処法も解説
2025年06月26日- 労働問題
会社が転勤を命じたにもかかわらず、従業員が転勤を拒否するケースも珍しくはありません。従業員にも諸事情はあるでしょうが、会社としては業務上の必要性から転勤を命じているのですから、従業員の個人的な都合を…
- 転勤
- 拒否
- 従業員
- 解雇
-

労務管理とは? ずさんだとヤバい? 人事・労務管理者の基礎知識
2025年06月23日- 労働問題
「労務管理」とは、従業員のさまざまな事項全般を管理する業務です。適切な労務管理ができていない企業では、労働者が気持ちよく働くことができません。そのため、生産性の低下や離職者の増加などにつながるリスク…
- 労務管理とは
企業法務コラム
- 企業法務・顧問弁護専門サイト
- 企業法務コラム
- 労働問題
- バックペイとは? 不当解雇で訴えられた企業の義務とリスク
お問い合わせ・資料請求