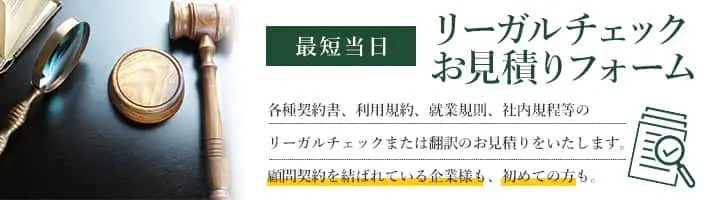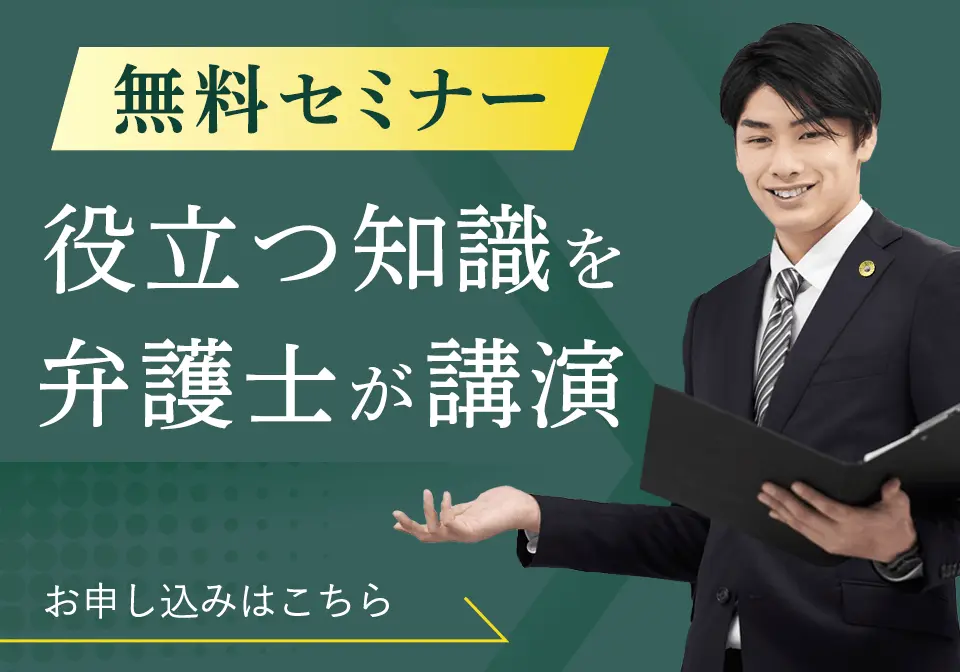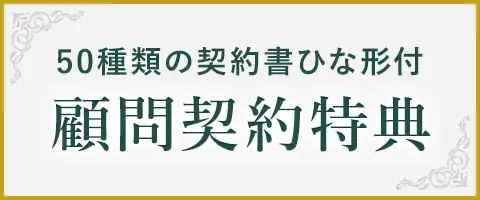- 企業法務・顧問弁護専門サイト
- 企業法務コラム
- 労働問題
- 解雇予告手当でトラブルを起こしたくない企業へ。弁護士が教える正しい知識
解雇予告手当でトラブルを起こしたくない企業へ。弁護士が教える正しい知識

昨今の経済情勢悪化などのやむを得ない事情によって従業員を解雇する場合、「30日前の解雇予告」あるいは「不足日数分の解雇予告手当」の支払いが必要です。
解雇予告手当については、計算方法や税金の処理方法を正確に把握していない方も多いのではないでしょうか?
この記事では解雇予告手当が必要なケースとそうでないケース、正しい計算方法など企業が把握しておくべき知識を、ベリーベスト法律事務所の弁護士がお伝えします。
1、解雇予告手当が必要となる条件
まずは、解雇予告手当そのものの基本的なルールをみていきましょう。
-
(1)そもそも解雇予告手当とは?
解雇予告手当とは、企業が30日以上前の解雇予告を経ずに従業員を解雇するときに支払うべきお金です。
企業が従業員を解雇するときには、少なくとも「30日前に解雇予告」しなければならないと定められています(労働基準法20条1項)。
解雇予告手当の支払いが間に合わない場合は?
しかし30日前に間に合わないケースもあるでしょう。
そういった場合には「30日に不足する日数分の解雇予告手当」を支払う必要があります(労働基準法20条2項)。 -
(2)解雇予告手当を企業が支払うタイミング
解雇予告手当の支払日は以下のとおりです。
① 事前に解雇予告する場合
解雇予告しつつ不足日数分の解雇予告手当を支給する場合には、遅くとも解雇日までに支払う必要がある
② 即日解雇する場合
30日分の解雇予告手当を支払って即時解雇する場合には、解雇と同時に支払う
解雇予告手当の支払いのタイミングが遅れると、従業員側が不満と不信感を抱いて企業側を訴えるなどトラブルの元になるので、遅延せずに支払いましょう。
-
(3)解雇予告手当を支払わなくてよいケース
懲戒解雇する場合、企業側が労働基準監督署に届け出て「解雇予告除外認定」を受ければ、解雇予告手当を支払う必要はありません(労働基準法20条1項但書、3項、19条2項)。
なお、このとき「除外認定」されなければ、懲戒解雇でも解雇予告手当が必要なので注意してください。
除外認定されるケースの具体例
除外認定されるのは、以下のような「従業員に非があるケース」です。- 従業員が企業のお金を盗んだ、横領した
- 賭博行為などをして職場の風紀を著しく乱した
- 悪質な経歴詐称をした
- 2週間以上無断欠勤して出勤の督促をしても応じない
- 遅刻や欠勤が多く、数回にわたって注意しても改善しない
- 他の事業へ転職した
また、天変地異などのやむを得ない事由で事業継続が不可能となった場合にも解雇予告や解雇予告手当の支払義務が免除されます。
問題社員のトラブルから、
2、基本的な解雇予告手当の計算方法を知ろう
解雇予告手当をどのように計算すればよいのか、月給制の従業員を例にみていきましょう。
-
(1)支払うべき日数の計算方法
解雇予告手当は「平均賃金」×「不足日数」によって計算します。
まずは支払われる日数の計算方法からみていきましょう。
日数は「30日に不足する日数」です。よって30-解雇までの日数
で計算できます。
たとえば解雇予告から解雇までの日数が10日であれば「30日-10日=20日分」の解雇予告手当が必要です。 -
(2)平均賃金の計算方法
次に「平均賃金」(労働基準法12条1項)の計算方法をみていきましょう。
① 平均賃金の計算式
平均賃金の計算式は以下のとおりです。平均賃金=(過去3か月分の賃金の合計額)÷(過去3か月の総暦日数)
過去3か月とは、解雇日の前日からさかのぼって3か月ですが、賃金の締切日がある場合は(通常は賃金の締切日があります)、直前の賃金の締切日からさかのぼって3か月になります(労働基準法12条2項)。
② 平均賃金の端数
平均賃金の端数については「銭未満」の部分を切り捨てます。
たとえば計算した結果が、5400.3456となった場合、平均賃金は5400.36円です。
解雇予告手当の端数については、原則として「円未満」の部分を四捨五入します。
なお、総暦日数とは、出勤日数ではなく、カレンダーの日にちすべてのことをいいます。
たとえば、1か月30日のうち、土日休みの人が20日勤務・10日休日だった場合、出勤日数は20日ですが、総暦日数では30日となります。
③ 賃金算定期間から除外される期間
以下の期間は平均賃金を計算する3か月から除外します(労働基準法12条3項)。- 業務上のケガや病気で休んだ期間(1号)
- 産前産後休業をとった期間(2号)
- 企業側の都合で休んだ期間(3号)
- 育児休業や介護休業をとった期間(4号)
- 試用期間(5号)
④ 平均賃金算定の基礎となる賃金や手当
過去3か月分の賃金には、以下のようなものを含みます。- 基本給
- 通勤手当
- 精皆勤手当
- 年次有給休暇の賃金
- 昼食代
- 確定したベースアップの賃金
- 未払い賃金
⑤ 賃金総額から控除
ただし次の賃金は賃金総額から控除します(労働基準法12条4項)。- 臨時に支払われた賃金(私傷病手当、お見舞金、結婚手当、退職金など)
- 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(半年に1回支給される賞与など)
- 通貨以外のもので支払われた賃金(法令や労働協約で定められていない現物支給)
-
(3)解雇予告手当の計算例
たとえば、解雇予告の不足日数が20日、過去3か月の暦日数が91日、過去3か月分の給与総額が90万円のケースを考えてみましょう。
この場合、以下のように計算します。平均賃金=90万円÷91日=9890.10(銭未満切捨て)
解雇予告手当=9890.10×20日=19万7802円 -
(4)最低保障額
解雇予告手当を計算するにあたって、賃金の全部または一部が日給制、時給制、請負制の場合、平均賃金は最低保障額を下回ってはいけません(労働基準法12条1項1号)。
3か月間に欠勤日数が多い場合に平均賃金が低くなりすぎてしまうため、このような制度が設けられています。
最低保障額の計算式は、以下のとおりです。(過去3か月分の賃金の合計額)÷(過去3か月分の実労働日数)×0.6
これまでご紹介してきた計算方法で算出された額が、最低保障額より少ない場合には、最低保障額を解雇予告手当の金額とします。
3、雇用形態別にみる、解雇予告手当の計算方法
次に雇用形態ごとに解雇予告手当の計算方法をご説明します
本章では、主に非正規雇用者の解雇予告手当の扱いについて解説いたします。
-
(1)パート・アルバイトの場合
パートやアルバイトの場合にも月給制の従業員と同様、不足日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。計算方法も同じです。
ただし、パートやアルバイトの場合、平均賃金が著しく低くなってしまう可能性があります。その場合には、「最低保障額」を基準として計算します。 -
(2)契約社員(有期労働契約)の場合
有期労働契約の場合、「契約期間中」に解雇するのであれば、解雇予告手当が必要となります。その場合の計算方法は原則的な計算方法と同じです。
ただし、契約期間が2か月以内の場合(※1)、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される場合(※2)は、解雇予告手当の規定が適用されません。
※1:所定契約期間を超えて継続雇用される場合を除きます(労働基準法21条2号)
※2:所定契約期間を超えて継続雇用される場合を除きます(労働基準法21条3号) -
(3)契約の更新をしない場合(雇止め)
一方、期間満了のタイミングで「契約の更新をしない」ケース、いわゆる雇止めは、契約期間の満了であって解雇ではありません。
労働基準法の解雇予告に関する規定が適用されないので、解雇予告や不足日数分の解雇予告手当の支払いは不要です。
ただし厚生労働省の告示により、雇止めであっても以下の場合には、「30日前の解雇予告」が必要とされています。- 契約が3回以上更新されている場合
- 1年を超えて継続雇用されている場合
なお、厚生労働省の告示によって要求されるのは「30日前の解雇予告」のみであり「解雇予告手当」は要求されていません。
そのため、雇止めのケースでは解雇予告手当の支払いは不要です。 -
(4)日雇労働者の場合
日雇労働者の場合、労働契約が「1日ごと」になるので、理屈としては継続雇用を前提とする「解雇予告手当」は発生しないのが原則です。
ただし、日雇労働者でも「1か月を超えて継続雇用」されている場合は解雇予告手当の規定が適用されます(労働基準法21条1号)。
よって、1か月を超えて継続雇用している日雇労働者を解雇する際には、解雇予告手当を計算して支給しなければなりません。 -
(5)試用期間中に解雇する場合
試用期間中に「14日を超えて継続雇用」されている場合は、解雇予告手当の規定が適用されます(労働基準法21条4号)。
4、解雇予告手当に源泉徴収は必要か?
解雇予告手当は「退職所得」の一種であり、源泉徴収が必要です。
もっとも、解雇予告手当の全額が課税対象になるわけではなく、(解雇予告手当-退職所得控除額)×1/2の金額が退職所得として課税されます。
退職所得控除額の最低額は80万円なので、源泉徴収の必要がない場合は多いと思われます。
従業員へ解雇予告手当を支給する際にはきちんと計算して源泉徴収を行い「退職所得の源泉徴収票」を作成して、1か月以内に解雇した従業員へ送付しましょう。
5、解雇後に必要となる手続き
従業員を解雇したら、企業としては以下のような手続きも必要となります。
-
(1)ハローワークでの手続き
まずはハローワークでの手続きを進めましょう。
企業がきちんと対応しないと従業員は雇用保険から失業保険の給付を受けにくくなり、後のトラブルにつながることも考えられるため、誠実に対応すべきです。
解雇日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」をハローワークへ提出しましょう。
それらと引き換えにハローワークから「離職票」が交付されます。
離職票は従業員が雇用保険を受給するために必要な重要書類です。受け取ったらすぐに解雇した従業員へと送付しましょう。
離職票の送付遅延は従業員との間でトラブルになりやすいため、素早く対応してください。 -
(2)社会保険の手続き
次に社会保険関係の手続きが必要です。
まず、解雇日の翌日から5日以内に年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出しましょう。提出が遅れると解雇したはずの従業員の保険料を請求されてしまう可能性があります。
次に従業員へ「資格喪失証明書」を送ります。
これは従業員が健康保険に加入するために必要な重要書類であるため、すぐに発送しましょう。 -
(3)解雇理由証明書の交付
解雇すると、従業員側から「解雇理由証明書」の交付を求められるケースがあります。これは「企業が従業員を解雇した理由を記載した書面」です。
労働基準法上、企業は従業員から解雇理由証明書を求められたら遅滞なく交付しなければなりません。請求されて交付しなかった場合、違法となってしまいます(労働基準法22条1項、2項)。
ただ、解雇理由証明書は「請求がなければ交付しなくてよいもの」です。
請求があってから作成・交付すれば問題ありません。
なお解雇理由証明書に記載した内容により、従業員が後に「解雇無効」として労働審判や訴訟などを提起することもあります。
解雇理由証明書を発行する際には、弁護士とも相談して後にリスク要因とならないよう適切な記載を行うべきでしょう。
問題社員のトラブルから、
6、まとめ
解雇予告手当は、支給すべきケースと支給しなくてもよいケースがありますが、支給を免除してもらうには「除外認定」を受けなければなりません。
また従業員の雇用形態によっても扱いが異なり計算方法も複雑です。
解雇の際には「そもそも解雇理由が認められるか」という問題があり、解雇理由がないのに解雇したら「不当解雇」として訴えられてしまうリスクが高まります。
解雇に不安がある場合、事前に弁護士にご相談ください。特に実際にトラブルになってしまったら一刻も早く法律家によるアドバイスを受けるべきです。
ベリーベストでは中小企業向けに顧問弁護士サービスを充実させています。
労災保険や雇用保険など労働保険関係、解雇、賃金などの労務管理についてお悩みがありましたら、ぜひとも一度ご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- 内容・ご事情によりご相談をお受けできない可能性もございます。
- ご相談者様が、法人格のない個人事業主様の場合、初回相談は有料となります。
同じカテゴリのコラム
-

減給は10分の1までしかできない? 減給の上限をケース別に解説
2025年06月30日- 労働問題
企業では従業員の不祥事や職務懈怠、能力不足、あるいは会社の業績不振など、様々な理由で従業員の減給を検討することがありますが、無制限に減給できるものではありません。減給の方法によっては、法律で「10分…
- 減給
- 10分の1
-

転勤を拒否する従業員を解雇できる? 解雇以外の正しい対処法も解説
2025年06月26日- 労働問題
会社が転勤を命じたにもかかわらず、従業員が転勤を拒否するケースも珍しくはありません。従業員にも諸事情はあるでしょうが、会社としては業務上の必要性から転勤を命じているのですから、従業員の個人的な都合を…
- 転勤
- 拒否
- 従業員
- 解雇
-

労務管理とは? ずさんだとヤバい? 人事・労務管理者の基礎知識
2025年06月23日- 労働問題
「労務管理」とは、従業員のさまざまな事項全般を管理する業務です。適切な労務管理ができていない企業では、労働者が気持ちよく働くことができません。そのため、生産性の低下や離職者の増加などにつながるリスク…
- 労務管理とは
企業法務コラム
- 企業法務・顧問弁護専門サイト
- 企業法務コラム
- 労働問題
- 解雇予告手当でトラブルを起こしたくない企業へ。弁護士が教える正しい知識
お問い合わせ・資料請求