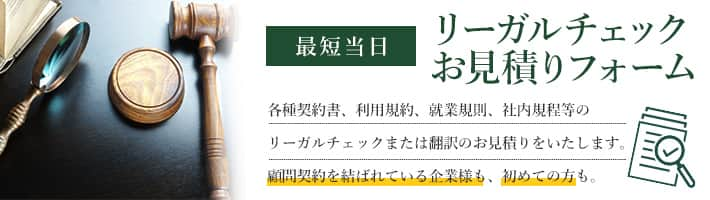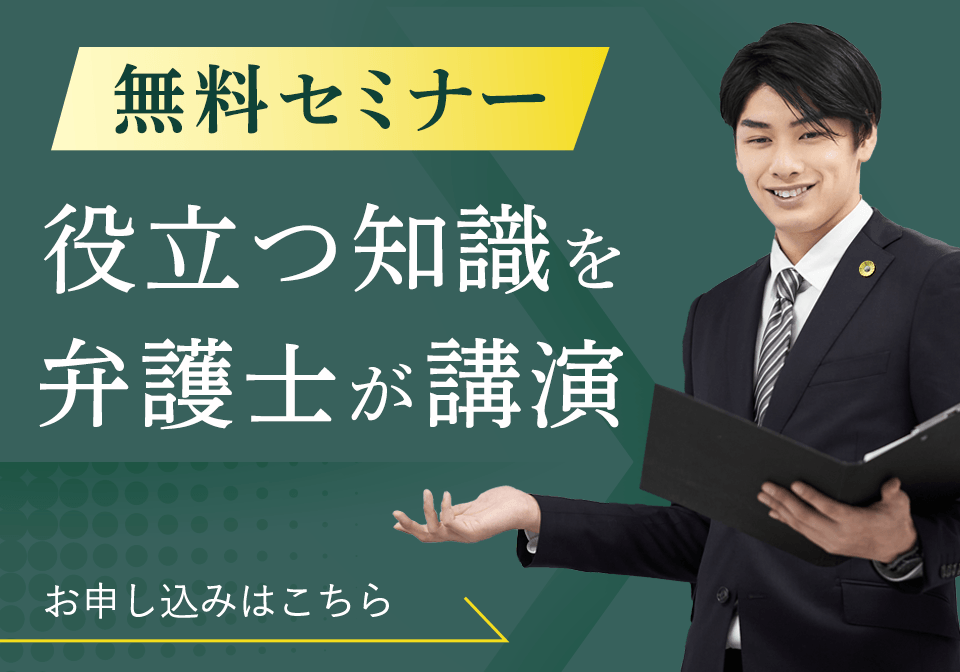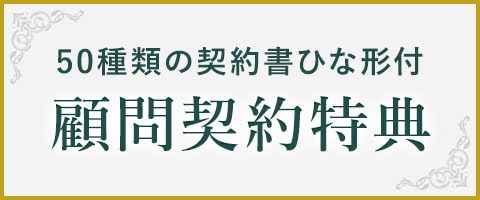- 企業法務・顧問弁護専門サイト
- 企業法務コラム
- 労働問題
- 残業代請求権の消滅時効期間が2年から5年に延長される? いま企業がするべきことは?

企業法務コラム
残業代請求権の消滅時効期間が2年から5年に延長される? いま企業がするべきことは?

2020年4月に改正民法が施行され、債権の消滅時効期間が原則的に「5年」に統一されます。
これにともない、現在「2年」とされている残業代請求権の消滅時効期間の見直しが議論されており、中には「5年」に延長すべきとの意見も出ています。
残業代請求権の消滅時効期間が延長されたら、企業や労働者へどのような影響が及ぶのか、またそれに向けて企業の人事担当者がするべきことなどを、弁護士が解説します。
1、残業代請求権の消滅時効期間とは?
-
(1)残業代請求権の消滅時効期間を知ろう
まず、本コラムのテーマである「残業代が請求できる期間」についてですが、それには「消滅時効」が関係しています。
消滅時効とは、一定期間債権者が権利行使をしない場合に権利が消滅する制度です。
残業代が未払いになっていても、消滅時効成立に必要な期間が経過し、企業が消滅時効を援用する意思表示をすれば、労働者は企業に残業代を請求できなくなります。
問題となっているのは、この「消滅時効成立に必要な期間」つまり「残業代が請求できる期間」が、近い将来、法改正により変わる可能性があることです。 -
(2)2020年4月から民法の消滅時効期間が変わる予定
現在の残業代を含む賃金の請求権の消滅時効期間は「2年」です(労働基準法115条)。
今の制度の場合、労働者が残業代を払ってもらっていなくても、2年間が請求期限となり、それを過ぎると残業代請求はできなくなる可能性があります。
ところで、2020年4月に施行される改正民法では、債権の消滅時効期間が原則的に「5年」に統一されます。
それに伴い、残業代を含む賃金の請求権についても消滅時効期間を変更する必要がないかが議論されており、中には、5年に延長するべきとの意見も出ています。
2、なぜ、残業代請求の消滅時効期間の延長が検討されているのか?
なぜ今のタイミングで残業代請求権の消滅時効期間を変更することが議論されているのか、また、5年に延長すべきとの意見が出ているのか、もう少し詳しく理由をみてみましょう。
-
(1)民法改正に伴う労働基準法改正の必要性
これについては「民法改正」との関係が密接です。
実は現在の民法では、月またはこれより短い時期によって定められた給料債権(多くの労働者の給料がこれに該当すると思われます。)の消滅時効期間は、たった「1年」です(民法174条1号)。
しかし、1年では短すぎて労働者に不利益が及ぶ可能性があります。
法律上は可能であるものの、実際、働きながら勤務先の企業へ残業代請求をするのは困難で、退職して残業代請求の準備をしているうちにあっという間に1年など経過してしまうということもあるでしょう。
そこで、労働基準法115条により、未払い賃金請求権の消滅時効期間を2年に延長している状況です。
ところが2020年4月に施行される改正民法では、先ほど説明した給料債権の消滅時効期間を1年とする規定が廃止され、債権の消滅時効期間が原則的に「5年」に統一されます。
そうすると、労働基準法の定める「2年」の方が民法の原則よりも短くなってしまい、「労働者保護のために残業代を含む賃金請求権の消滅時効期間を2年に延長した」労働基準法の意味がなくなってしまいます。
そこで、民法改正にともなって、労働者の権利を拡充する方向で労働基準法も改正し、賃金等請求権についても消滅時効期間を変更することが議論され、中には、5年に延長すべきという意見が出てきています。 -
(2)サービス残業の根絶
政府は日本国内で横行してきた「サービス残業」の悪しき風習を根絶しようしています。
残業代請求権の消滅時効が5年に延長されれば、いざ不払い残業代請求を受けた場合の影響が大きくなるので、企業側もきちんと残業代を支給するようになる効果が期待できます。
労働者が働いた分の給料を受け取るのは当然の権利ですし、労働者を守るための労働基準法がかえって労働者の権利を制限する状況は明らかに不合理です。
このことを考えると、残業代を含む賃金請求権の消滅時効期間を現行の2年よりも長く、たとえば5年に延長されるべきとの意見が出るのは当然のことといえます。
3、有給休暇の取得期間も延長される可能性あり
実は残業代請求権の消滅時効期間の変更の議論と同時に、有給休暇の取得期間についても議論されています。
有給休暇とは、就労義務が免除される一方で、給料を受け取ることができる休暇です。
労働者は勤続年数に応じて1年に定められた日数の有給休暇を取得できます(労働基準法39条)。有給休暇には仕事をしなくても欠勤扱いにならず、通常どおりの給料が支払われます。
有給休暇を消化できなかった場合、繰り越しが認められますが、現在繰り越しできるのは「2年」までです。
有給休暇の請求権は2年で時効にかかるので(労働基準法115条)、取得できなかった有給休暇は過去の分からどんどん消滅していきます。
そこで、残業代等の賃金の請求権の消滅時効期間の見直しの議論に合わせて、有給休暇の請求権の消滅時効期間についても、議論されています。
もし有給休暇の消滅時効期間が5年になれば、年間20日の有給休暇が認められる労働者の場合、最大100日分(20日×5年)有給休暇請求権を保有できることになります。
ただし、有給休暇については、そもそも権利が発生した年の中で取得することが想定されており、未取得分の翌年への繰り越しは制度趣旨に鑑みると例外的なものですから、有給休暇の消滅時効期間を長くすることは、制度の趣旨に合致せず、有給休暇取得率の向上という政府の政策に逆行することになります。
したがって、必ずしも賃金請求権と同様に取り扱う必要はないとの意見が強いです。
問題社員のトラブルから、
4、適切に残業代を支払っていない企業は注意が必要
以上、少なくとも残業代請求権(賃金請求権)については消滅時効期間が5年に延長される可能性があると言えるでしょう。
実際に残業代請求権の時効が5年に延長されたら、企業側にはどのような影響が及ぶのでしょうか。
-
(1)労働者から5年分の高額な未払い残業代請求をされる可能性がある
注意しなければならないのは、未払い賃金のある企業です。 これまでは、労働者にきちんと残業代を払っていなくても、残業代発生から2年が経過すれば労働者は残業代を請求することができなくなっていました。
しかし、仮に残業代請求権の消滅時効期間が5年に延長されると、退職してから5年以内の元労働者から未払い残業代請求をされる可能性があります。2年であればさほど高額にならなかった未払い残業代も、5年分となると相当金額がかさみます。
辞めた労働者からいきなり「数百万円の残業代を請求する内容証明郵便」が届いたり、労働審判等を申し立てられたりする可能性があります。
また、今回の民法改正やそれに伴う残業代請求権の消滅時効期間の見直しの議論等がニュースなどで流れることにより、これまで未払い残業代を意識していなかった労働者たちが請求権に気づき、残業代を請求する可能性もあります。 -
(2)遅延損害金が高額になる可能性がある
残業代などの未払い賃金等請求権には「遅延損害金」が加算されることにも注意が必要です。
法律上、残業代請求権には年6%の割合の遅延損害金が加算され続けます(商法514条)。退職後の労働者の場合には年14.6%にもなります(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項、同法施行令1条)。
2年であればさほど高額ではなかった遅延損害金も、5年になると膨大に膨らむリスクがあります。 -
(3)付加金や罰則、社会的評価の低下のリスクがある
労働者から未払い残業代を請求する訴訟を提起されると「付加金」として未払い残業代の元金と同等の金額の支払を追加的に命じられる可能性もあります。
残業代未払いが悪質と判断されれば、労働基準監督署から摘発を受けて懲役刑や罰金刑を適用される可能性もありますし、「残業代未払い」と大々的に報道されることによる企業イメージの低下の問題などもあります。
5、残業代請求権の時効延長の前に、今から企業がするべき5つの対策
残業代等の未払い賃金請求権の消滅時効期間の延長が議論されていることなどについて、企業としては今後どのように対処するのが良いのでしょうか?
-
(1)残業代の精算
まずは現在未払いとなっている残業代の精算を行いましょう。
これまで時間外労働をした労働者に適切に残業代を支払っていなかったなら、一度どの程度未払いになっているかを精査して、まとめて支給してしまうことをおすすめします。
支払をすれば、未払い残業代の一括請求をされるリスクがなくなります。 -
(2)タイムカードなどの勤怠管理の適正化
次に重要なのは、勤怠管理の適正化です。
勤怠管理をきちんと行っていなかった場合、実際に残業代を精算しようとしてもどの程度の金額が未払いになっているのか把握できないケースもあるのではないでしょうか。
日頃からきっちりタイムカードや日報、勤怠管理ソフトなどを使って労働時間の管理と把握をしましょう。 -
(3)定額残業代制度の導入
残業代を労働基準法の原則どおりに計算して支払うのが負担になりすぎるという場合、「定額残業代(固定残業代)制度」の導入をおすすめします。
定額残業代制度とは、毎月一定の残業が行われることを折り込み済みとし、定額の残業代を支払う制度です。毎月必ずしも残業代を計算しなくても、一定額の残業代を含む給料を支給すれば足ります。
ただし定額残業代制度を導入するには、雇用契約書や就業規則に定額残業代を導入していることを明記し、給与明細にも固定給部分と残業代部分を明確に区分して分かるようにしておく等の必要があります。
また、賃金の総額を変更せずに定額残業代制度を導入する場合は、労働条件の不利益変更となる可能性があるため、労働契約書や就業規則の作成方法等定額残業代制度を導入するにあたっては、弁護士へご相談されることをおすすめいたします。 -
(4)歩合給制度の導入
残業代対策としては歩合給制度も有効です。
歩合給制度とは、労働者が一定の成果を上げた場合その成果に応じて給料を支払う制度です。歩合給の場合、残業代は以下の合計額によって計算されます。- 基本給部分 時給×1.25(割増率)×残業時間
- 歩合給部分 時給×0.25(割増率)×残業時間
このように歩合部分については割増率が0.25となるので、通常どおりに計算するより残業代を抑えやすくなります。
歩合制を導入できる労働者については積極的な活用を検討する価値があります。
ただし、歩合制を導入すると、デメリットもあります。
労働者の過重労働が発生しやすくなったり、成果が出せなければ給与が少なくなったりしますので、生活に不安を覚えた労働者の離職が増える可能性などが考えられます。
メリット・デメリットを踏まえた上で、導入を検討する必要がありますので、労務問題に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめします。 -
(5)雇用契約書と就業規則の見直し
上記で紹介したような「定額残業代」や「歩合給」を導入するには、きちんと雇用契約書や就業規則に明記する必要があります。特に定額残業代については、就業規則の内容が不適切であったため無効とされ、企業側の反論が認められなかった例も多数あります。
労働者から残業代請求をされたとき、企業が高額の支払命令を受けることを避けるには、就業規則や雇用契約書で契約内容をきちんと規定しておかねばなりません。
現在の規定内容に不安がある企業は、一度労務管理の状況と共に見直しをすることをおすすめします。
問題社員のトラブルから、
6、まとめ
今後、未払い残業代の請求期間が5年に延長される可能性があることを前提として、企業側もしっかり対応できるようにしておくべきです。
適切に労働法務対策を行うには、専門の法的知識を持った弁護士によるサポートが必要です。定額残業代制や歩合制を導入する際にも、弁護士がアドバイスや各種の書面作成、社内の労務管理方法改善についてのアドバイスを行います。
勤怠管理、残業代関係でお悩みの企業ご担当者さまは、お気軽にベリーベスト法律事務所までご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
同じカテゴリのコラム
-

労働審判とは? 労働者から訴えられた際に企業が対応すべきこと
2024年07月17日- 労働問題
労働者との間で未払い残業代や不当解雇などのトラブルが発生した場合、労働者から労働審判の申し立てをされることがあります。労働審判は、訴訟に比べて迅速かつ柔軟な解決が可能な手続きですが、限られた期間で対…
- 労働審判
- 訴訟
- 対応
-

賞与(ボーナス)の支給基準とは? 支給額を減らすのは違法か合法か
2024年06月27日- 労働問題
企業から労働者に対する賞与の支給は、法的な義務ではありません。賞与の有無および支給額の算出方法などは、企業が独自に定めることが可能です。例外的に、賞与の定め方によっては支給義務が生じるため、一方的に…
- 賞与
- 基準
- 減額
-

謹慎処分とは? 従業員から不当だと言われた場合の対処法
2024年06月20日- 労働問題
謹慎処分には、懲戒処分と業務命令がありますが、どちらに該当するかにより、労働者への制限の範囲が違いますので、謹慎処分をする際には根拠を明確にすることが大切です。また、謹慎処分は、労働者の権利を制約す…
- 謹慎処分
企業法務コラム
- 企業法務・顧問弁護専門サイト
- 企業法務コラム
- 労働問題
- 残業代請求権の消滅時効期間が2年から5年に延長される? いま企業がするべきことは?
お問い合わせ・資料請求