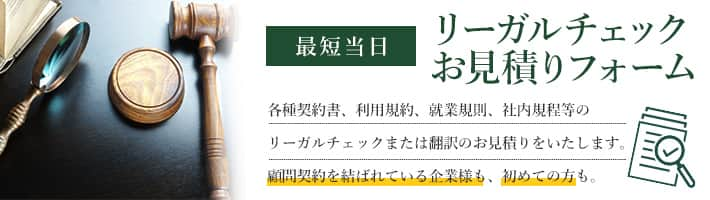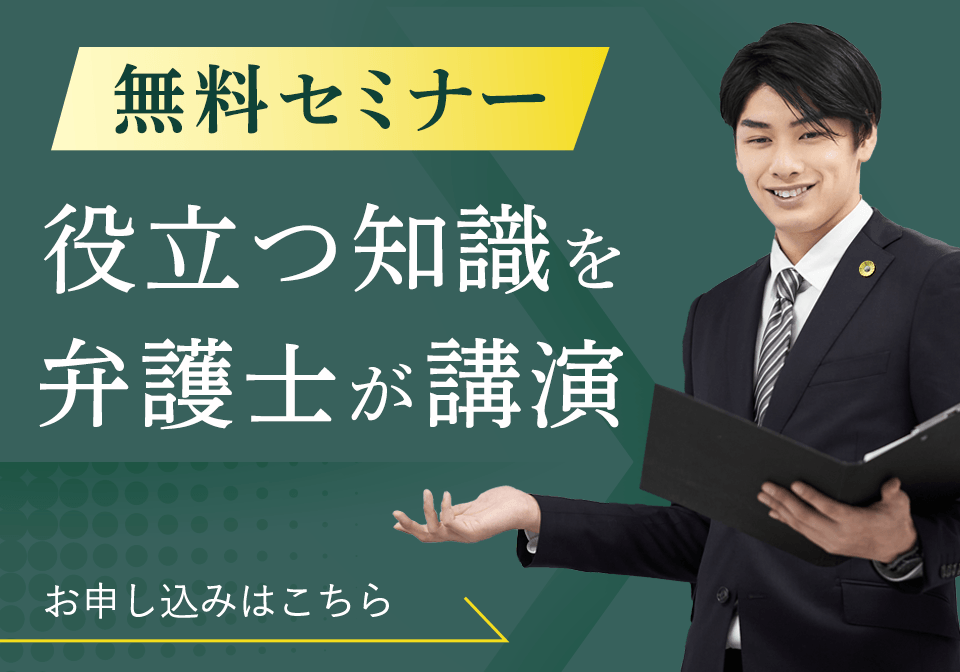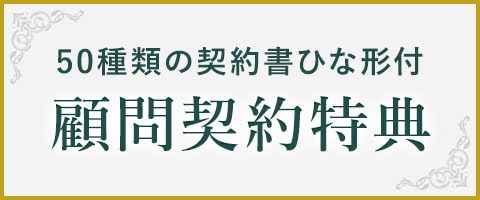- 企業法務・顧問弁護専門サイト
- 企業法務コラム
- 労働問題
- フレックスタイム制を導入! 会社が理解しておくべき残業代の正しいルール

企業法務コラム
フレックスタイム制を導入! 会社が理解しておくべき残業代の正しいルール

生産性を向上させるため、労働者に働き方に関する裁量を与えて柔軟な勤務時間制を採用する会社が増えてきています。フレックスタイム制もこのような柔軟な勤務時間制のひとつと言えます。
しかし、会社としてフレックスタイム制を導入する際には、フレックスタイム制に適用される労働法上のルールを正しく理解しておく必要があります。特に、フレックスタイム制では残業代を支払う必要がないと思い込んでいる方もいらっしゃいますが、それは誤りです。
このような間違った理解の下、「残業代を支払わなくて良いのだから」と労働者の勤務時間の管理を怠ると、後に労働者との間でトラブルに発展しかねません。本コラムでは、フレックスタイム制の仕組みや、フレックスタイム制における残業の考え方について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、フレックスタイム制の仕組み
まず、フレックスタイム制における労働時間の考え方と、導入する際に必要な労働法上の手続きについて見ていきましょう。
-
(1)フレックスタイム制における労働時間の考え方
フレックスタイム制は、一定の期間(清算期間)についてあらかじめ定めた総労働時間(所定労働時間)の範囲内で、労働者が日々の始業時刻や終業時刻、労働時間を自ら決定することができる制度です(労基法32条の3)。
フレックスタイム制では、働かなければいけない時間の総量(総労働時間)は清算期間単位で決まります。
そのため、ある1日の労働時間が少なかったとしても、労働者の判断で他の日に多めに労働するなどの柔軟な対応が可能です。
また、フレックスタイム制では、コアタイムとフレキシブルタイムが設けられることがあります(労基法32条の2第1項4号、労基法施行規則12条の3第1項2号)。
コアタイムとは
労働者が必ず勤務して業務を行わなければならない時間帯を指します。
フレキシブルタイムとは
労働者がその選択により労働することができる時間帯のことを指します。
たとえば、フレキシブルタイムを指定しなければ、従業員が深夜時間に勤務して深夜割増賃金が発生してしまうこともありうるため、従業員が深夜時間に勤務しないように、フレキシブルタイムとして深夜以外の時間帯を指定するなどの用いられ方がされています。
-
(2)フレックスタイム制を導入する際に必要な労働法上の手続き
フレックスタイム制を導入する際には、労働基準法に従い、以下の2つの手続きを取る必要があります。
① 就業規則などへの規定
フレックスタイム制を導入する際には、就業規則やその他の社内規則の中で、始業および終業の時刻を、労働者の決定に委ねる旨を定める必要があります。
フレキシブルタイムを定める場合には、フレキシブルタイムが極端に短いと、始業・終業時刻が労働者に委ねられているとはいえないことになるため、注意が必要です。
なお、コアタイムとフレキシブルタイムを設定する場合には、その時間帯を就業規則にも規定しておくことになります。
就業規則の一例
フレックスタイム制が適用される従業員の始業および終業の時刻については、従業員の自主的決定に委ねるものとする。ただし、始業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午前6時から午前10時まで、終業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午後3時から午後7時までの間とする。
参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き 4P(PDF:3.71MB)
② 労使協定で所定の事項を定める
フレックスタイム制を導入する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合があるときには労働組合と、そのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結して、フレックスタイム制に関する所定の事項を定めておく必要があります。
また、清算期間が1か月を超える場合には、労使協定を労働基準監督署長に届け出る必要があります(労基法32条の3第4項)。
労使協定で定めるべき事項は次のとおりです(労基法32条の3第1項、労基法施行規則12条の3第1項)。
労使協定で定めるべき事項- 対象となる労働者の範囲
- 清算期間
- 清算期間における総労働時間
- 標準となる1日の労働時間
- コアタイム
- フレキシブルタイム
- 清算期間が1箇月を超える場合には、労使協定(労働協約を除く)の有効期間
- 清算期間の起算日(労基法施行規則12条の2第1項)
なお、コアタイムとフレキシブルタイムについては任意とされています。
2、フレックスタイム制に時間外労働(残業)はない?
フレックスタイム制には時間外労働の考え方がないと勘違いしている方もいらっしゃいますが、これは誤りです。
フレックスタイム制における時間外労働の考え方について、正しく理解しておきましょう。
-
(1)理解しておきたい「清算期間」と「総労働時間」
フレックスタイム制における時間外労働を理解するためには、「清算期間」と「総労働時間」の考え方を理解しておく必要があります。
① 清算期間とは?
「清算期間」とは、フレックスタイム制における労働者の労働時間を定める単位となる期間のことです。
清算期間は、最長3か月までの期間を労使協定で定めることができます。
② 総労働時間とは?
そして、清算期間中に労働者が労働すべき時間数が「総労働時間」です。
総労働時間は、160時間というように各清算期間を通じて一律の時間を定める方法のほか、清算期間における所定労働日を定め、所定労働日1日当たり7時間というような定めをすることもできます。
なお、清算期間の実労働時間が、総労働時間に満たない場合、賃金の減額や、法定労働時間の総枠の範囲内で、次の清算期間に繰り越すことができます。
反対に、清算期間の実労働時間が、総労働時間を超える場合には、次の清算期間に繰り越すことはできません(昭63.1.1基発1号)。 -
(2)フレックスタイム制でも時間外労働(残業)は発生する
清算期間中に総労働時間を超える労働を行った場合、超過分は時間外労働として取り扱われます。また、下記(3)の法定労働時間の総枠を超える労働時間については、法定時間外労働として取り扱われます。
時間外労働が発生した場合は、清算期間ごと、あるいは、各月ごとに時間外労働手当(残業代)を精算しなければなりません。
問題社員のトラブルから、
3、フレックスタイム制における法定労働時間
-
(1)フレックスタイム制の基本的な労働時間の考え方
フレックスタイム制では柔軟な働き方が可能となっていますが、36協定の定めがなければ、清算期間内を平均し、1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間(40時間又は44時間)を超えてはいけません(労基法32条の3第1項、32条1項、40条1項、労基法施行規則25条の2第1項、同4項)。
つまり、清算期間全体では
週の法定労働時間×清算期間中の暦日数÷7
(法定労働時間の総枠)
まで、働いてよいことになります。
-
(2)完全週休二日制の場合
もっとも、完全週休二日制で、1日8時間というごく一般的な労働をしている場合でも、曜日の巡りによって、週平均40時間を超えてしまうことがあります。
そのため、完全週休二日制の場合、労使協定の定めにより、清算期間全体で、
清算期間中の所定労働日数×8時間
を超えるまでは働いてもよいこととされています(労基法32条の3第3項)。
-
(3)清算期間が1か月を超える場合
また、清算期間が1か月を超える場合には、36協定の定めがなければ、清算期間を1か月ごとに区分した各期間の労働時間が、
各期間の暦日数×50時間÷7
を超えてはいけません(労基法32条の3第2項)。
-
(4)注意したい時間外労働(残業)の上限(36協定と労働基準法)
フレックスタイム制の場合にも、時間外労働に関する上限規制は適用されます。
時間外労働の上限は、「① 36協定」と「② 労働基準法」の2つのルールによって定まります。
① 36協定
そもそも、会社が労働者に時間外労働をさせるためには、労使間で労働基準法第36条第1項に基づく協定(36協定)を締結する必要があります。
36協定の中では、時間外労働の上限も定める必要がありますので、フレックスタイム制の場合にもこの上限を順守しなければなりません。
② 労働基準法
さらに、労働基準法36条4項は、時間外労働の上限を原則として月45時間・年360時間と定めています。
また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合であっても、以下の範囲内に収まるようにしなければなりません(労基法36条5項、6項)。
なお、清算期間が1か月間を超える場合には、各種上限規制は、1か月平均50時間を超えた時間について適用されます。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」のすべてが1月あたり80時間以内
- 時間外労働が45時間を超える月が6か月以下
4、フレックスタイム制における時間外労働手当(残業代)の計算方法
では、フレックスタイム制において、時間外労働が発生した場合、時間外労働手当はどのように計算されるのでしょうか。
-
(1)時間外労働手当(残業代)の計算方法
フレックスタイム制における時間外労働手当は、以下の計算式により算出できます。
時間外労働手当=1時間あたりの基礎賃金×時間外労働(残業)の時間数×割増率
-
(2)1時間当たりの基礎賃金
「1時間あたりの基礎賃金」は以下の計算式により求められます。
1時間あたりの基礎賃金=基礎賃金÷1年間における1月平均所定労働時間
「基礎賃金」は、給与の総額から以下の手当や賃金を控除して算出された金額のことを指します(労基法37条5項、労基法施行規則21条)。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
-
(3)時間外労働の時間数
また、時間外労働の時間数は、法定時間外労働と所定時間外労働(法内残業)と休日労働(法定休日における労働)で区別をする必要があります。
① 法定時間外労働とは?
法定時間外労働とは、清算期間の実労働時間(休日労働を除く)が法定労働時間の総枠(=1週間の法定労働時間×清算期間の暦日数÷7(完全週休二日制の場合:清算期間の所定労働日数×8時間))を超えた時間数のことです。
② 所定時間外労働とは?
所定時間外労働とは、総労働時間が清算期間内における法定労働時間の総枠よりも短い場合の、実労働時間(休日労働を除く)が総労働時間を超え、法定労働時間の総枠に満ちるまでの時間数のことです。
たとえば、1か月の清算期間における総労働時間が160時間と定められている場合のある月の暦日数が31日のときは、清算期間における法定労働時間の総枠は177.1時間となります。
そして、清算期間の休日労働を除く実労働時間が、180時間の場合、17.1時間が所定時間外労働となり、2.9時間が法定時間外労働となります。
法定時間外労働については、法定の割増率により割増された賃金を支払う必要がありますが、所定時間外労働については、就業規則等で特に定めがない限り、割増されていない通常の賃金を支払うことで足ります。 -
(4)清算期間が1か月を超える場合
ただし、清算期間が1か月を超える場合は、法定時間外労働時間の算出方法が異なり、次のとおり、各月ごとの計算と清算期間全体の計算が必要となるため、注意が必要です。
① 清算期間における法定労働時間の枠数を算出します。
1週間の法定労働時間(40時間)×清算期間の暦日数÷7日
※清算期間が1箇月を超える場合には、特例措置対象事業場についても、週40時間が法定労働時間となります(労基法施行規則25条の2第4項)。
② 週平均労働時間が50時間となる各月の労働時間を算出します。
50時間×各月の暦日数÷7日
③ 各月の実労働時間(休日労働を除く)から②を差し引き、週平均50時間を超える労働時間数を算出します。
この超過時間による時間外労働を当該月の時間外労働手当として清算します。
④ 実労働時間(休日労働を除く)から、③と①を差し引きます。
清算期間を通じた実労働時間-③で算出した各月の超過時間の合計-①
この時間外労働を清算期間の最終月の時間外労働手当として清算します。
また、上記に加え、各月ごとに休日・深夜の割増賃金の支払いも必要となります。
-
(5)時間外労働手当(残業代)の割増率に注意
注意しなければならないのは、フレックスタイム制であったとしても、法定時間外労働に対しては割増賃金を支払わなければならないという点です。
割増率
割増率は、以下のとおりです。
所定時間外労働(法内残業) 割増なし(通常の賃金) 通常の法定時間外労働 25%以上 法定時間外労働(月60時間超)
※令和5年4月より中小企業も対象50%以上 深夜労働 25%以上 休日労働 35%以上 法定時間外労働かつ深夜労働 50%以上 休日労働かつ深夜労働 60%以上
※深夜労働以外は、割増分だけでなく、通常の時間給分も支給されるため、(1)の計算式に割増率を代入する際には、100%を加算します。
問題社員のトラブルから、
5、フレックスタイム制導入にあたり理解しておくべき3つのポイント
フレックスタイム制を導入した場合、労働者の勤怠管理などに関するルールがどのようになっているかわかりにくい部分もあるでしょう。
以下では、フレックスタイム制に関して疑問を生じやすい3つのポイントについて解説します。
-
(1)遅刻・早退の取り扱い
フレックスタイム制でコアタイムが定められている場合、コアタイムに関して遅刻・早退が有り得ます。
この場合労働者は、通常の勤務時間制を採用している場合と同様、就業規則やその他の社内規則にある、遅刻、早退のルールに従う必要が生じます。
コアタイムに遅刻をしても、総労働時間以上勤務している場合には、当然に減額ができるわけではなく、就業規則内に減給の制裁を設け、労基法91条の範囲内で減給の制裁が認められるに過ぎないことに注意が必要です。
一方コアタイムを設けない、完全フレキシブルのフレックスタイム制の場合には、そもそも遅刻・早退という概念が存在しません。 -
(2)有給休暇の取り扱い
フレックスタイム制が適用される労働者が有給休暇を取得した場合、「標準となる1日の労働時間」分の時間数、労働をしたものと取り扱われます(平30.12.28基発1228第15号)。
「標準となる1日の労働時間」については、フレックスタイム制の導入に必要な労使協定の中で定める必要があります。 -
(3)フレックスタイム制を適用する労働者の範囲について
会社としては、フレックスタイム制を全労働者に適用しても良いですし、一部の労働者や部署のみに適用することも可能です。また、対象者や部署ごとに清算期間を変えることも問題ありません。
なお、フレックスタイム制を適用する労働者の範囲や適用される清算期間は、労使協定の中で定めておく必要があります。
(1)から(3)の各点については、あらかじめ決めて、労働者にわかりやすく周知しておかなければ、労働者とのトラブルや紛争が発生しやすくなるため注意しましょう。
6、まとめ
フレックスタイム制を採用している場合であっても、時間外労働などに関するルールは適用されますので、会社として労働者の勤務時間などを適切に管理する必要があります。
また、フレックスタイム制を導入するにあたっては、就業規則を含めた社内規定の整備が必要になります。
会社としてのコンプライアンスや、後の労働者との紛争を防止する観点を踏まえると、労働法の内容を踏まえて制度を導入しなければなりません。
フレックスタイム制の導入を検討している、またフレックスタイム制に関して労働者とのトラブルへの対応を迫られている担当者の方は、ぜひベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
同じカテゴリのコラム
-

労働審判とは? 労働者から訴えられた際に企業が対応すべきこと
2024年07月17日- 労働問題
労働者との間で未払い残業代や不当解雇などのトラブルが発生した場合、労働者から労働審判の申し立てをされることがあります。労働審判は、訴訟に比べて迅速かつ柔軟な解決が可能な手続きですが、限られた期間で対…
- 労働審判
- 訴訟
- 対応
-

賞与(ボーナス)の支給基準とは? 支給額を減らすのは違法か合法か
2024年06月27日- 労働問題
企業から労働者に対する賞与の支給は、法的な義務ではありません。賞与の有無および支給額の算出方法などは、企業が独自に定めることが可能です。例外的に、賞与の定め方によっては支給義務が生じるため、一方的に…
- 賞与
- 基準
- 減額
-

謹慎処分とは? 従業員から不当だと言われた場合の対処法
2024年06月20日- 労働問題
謹慎処分には、懲戒処分と業務命令がありますが、どちらに該当するかにより、労働者への制限の範囲が違いますので、謹慎処分をする際には根拠を明確にすることが大切です。また、謹慎処分は、労働者の権利を制約す…
- 謹慎処分
企業法務コラム
- 企業法務・顧問弁護専門サイト
- 企業法務コラム
- 労働問題
- フレックスタイム制を導入! 会社が理解しておくべき残業代の正しいルール
お問い合わせ・資料請求